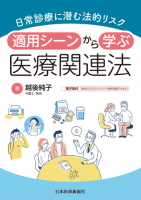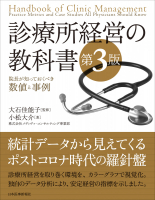お知らせ
【識者の眼】「病院統合のゴール」藤井美穂
2025年4月1日、新病院への移転が行われた。筆者が勤務していた総合病院と、同じ法人内の単科病院の2院が統合し、新設された病院に引っ越したのだ。
人口減少や高齢化、それに伴う地域の縮小と医療機能の地域間格差、医療費の抑制による病院運営の厳しさなどを背景に、病院統合が各地で進んでいる。一方、日本の大学も大学革新力創出指数にみる有力論文数、引用論文数の落ち込みから、研究力の地盤沈下と報じられており、大学の国際化認証スコアを上げ、研究力を上げる取り組みのひとつとして、統合再編に着手しはじめた。病院統合と大学統合は、その目的は異なっていても、歩んできた歴史土壌の異なる2つの組織が理念を共有し、同じ目標に向かって歩き始めることに違いはないだろう。

病院管理者は、医療機能の充実や患者の利便性向上など、統合後のメリットを考える一方、統合移転で必要になる新棟の建設なども含め、経営収支の見込みを綿密に算出し、統合にふみきることと思う。しかし、一般的に現場の職員は統合の目的や統合後の方針について、病院幹部ほど明確に理解していないことが多いのではないだろうか。
当院でも統合の1年以上前から人事交流が始まり、両病院の同一部署間で会議が何度となく持たれていたはずだった。しかし、2025年4月に入り実際に診療が始まってみると、これまで話し合いに上がってこなかった、小さな食い違いに気づく。組織間の文化の違いとも言える微妙な違いだが、両病院それぞれが業績を上げ自信を持って診療してきた故に、新たな道を進むにはもう少し時間がかかりそうだ。
統合が成功するための要因として、統合の目的を明確に設定し、関係者間で共有することが重要であると言われる。さらに、統合後に経営効率が上がったり、各部門の職員数に余裕ができたりすることで適正な配置が組めるようになり、医療の質が上がるなどの具体的な実績が示されることも重要なポイントであると指摘される。
ある病院統合の成功事例で、成功要因は新病院のめざす医療方針を病院内外に広報し続けたこと、とあった。そして、病院の意思決定機関の定例会議の議事録を公開し、職員に病院の歩むべき方向性を徹底的に「見える化」し、共有したという。
当院の統合を成功させるには、単なる情報の共有にとどまらず、すべての職員が統合の目的を理解する話し合いの場を持ち、統合によるシナジーを達成するために、各自がどのように行動すべきか、主体的に考える協働の土壌をつくり上げることが必須であると感じている。
藤井美穂(社会医療法人社団カレスサッポロカレス記念病院次席院長)[病院統合][統合再編][病院運営]