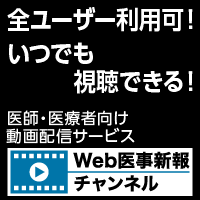お知らせ
【識者の眼】「眠ることの恐怖」西 智弘
No.5143 (2022年11月19日発行) P.64
西 智弘 (川崎市立井田病院腫瘍内科/緩和ケア内科)
登録日: 2022-11-09
最終更新日: 2022-11-09
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
患者から「眠ることが怖い」と訴えられたことはあるだろうか。
一般診療に従事していると「眠れなくて困る」訴えには頻繁に遭遇するし、おそらくはこの読者の多くも「もっと眠りたい」という満たされない思いをお持ちの方ばかりであろう。
しかし、緩和ケアの現場においてはこの「眠りたくない」苦痛の訴えにしばしば遭遇する。では、いわゆる終末期の患者たちはなぜ「眠ることが怖い」と訴えるのであろうか。
そのひとつの「わかりやすい」答えは、「眠ってしまうと、二度と目が覚めないのではないか」という恐怖である。睡眠と覚醒のリズムが崩れだし、目をあけていられる時間も短くなってくる中で、自らの死期が近くなってきていることを感じ取る。「ここで目をつむってしまったら二度と開けられることはないのではないか」という怖さは、私たちにとっても理解しやすい。もちろん、実際の患者でこのように理由づけをされる方もいる。
しかし、そのような「わかりやすい」解釈に飛びついてしまい、失敗する事例もある。たとえば、ある40代の乳癌患者の事例をご紹介しよう(個人情報保護のためフィクションを含む)。彼女は、骨転移から脊髄圧迫症候群をきたして下半身不随となった後、緩和ケアに専念するために当院へ転院してきた。肺や肝臓にも転移が広がった彼女の余命はおそらく1カ月以内と思われたが、しっかりと気丈に振る舞い、回診時には笑顔が見られることもあった。そんな彼女が転院してきて2週間くらいで、「眠ることが怖い」と訴えた。その理由も尋ねたが彼女は「言葉にできない」とのこと。夫と我々は、「こんなに眠ってしまっていいのか、目が覚めないのでは、という怖さはよくあること」と情報共有をし、夫は「体がしんどいのだから眠たいときは寝ていいんだよ」と言い、我々も「睡眠と覚醒のリズムが崩れているだけで、大丈夫ですよ」と声をかけたが、彼女の顔が晴れることはなかった。
そんなとき、ある看護師が「彼女が本当に悩んでいるのは『目が覚めないのでは』という怖さではなく、自身ができることが一つひとつ剝ぎ取られていく怖さではないか」と言った。つまり、彼女は主婦として、妻として、一人の女性として生きてきた中で、病気によって自由を奪われ、またその役割も奪われていった。さらに、ここにきて「自ら目を覚まし、また眠る」機能すらも自由にならなくなってきている。これからさらに、私は何を喪うのだろう……という怖さ。それは筆舌に尽くしがたいのではないか、とその看護師は考察したのだ。
それであれば、かけるべき言葉はまったく違う。夫や我々が、その考察に基づいて本人との関係性を見直し、安易な励ましではなく「あなたの今のままで。私たちはいつでも近くにいる」ことを言葉ではなく態度で示したことで、次第に「眠ってしまうことの恐怖」は訴えなくなり、表情も穏やかになっていったのである。
緩和ケアの現場ではあらゆる表現を用いて患者がその苦痛を訴える。安易な解釈に飛びつくのではなく、多様な角度から深く考えを馳せることが何より大切である。
西 智弘(川崎市立井田病院腫瘍内科/緩和ケア内科)[緩和ケア]