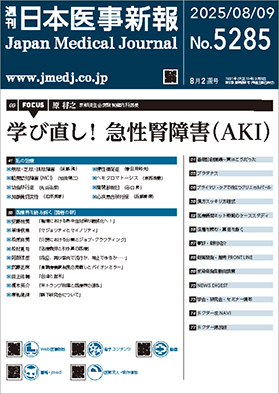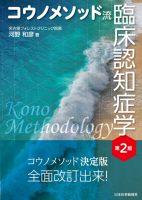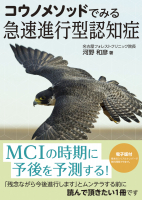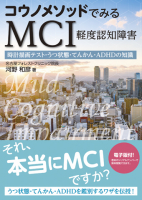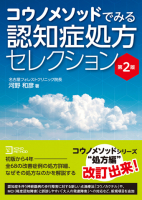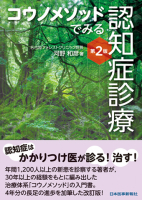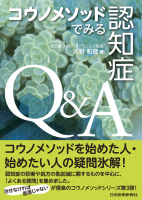お知らせ
適応拡大が続く脳血栓回収療法において,実践面で注意すべきことは?

突然に重度の脳障害に陥る塞栓性脳梗塞に対する脳血栓回収療法は,ステントや吸引カテーテルなどのデバイスが次々と開発され,近年目覚ましい進歩を遂げています。また,従来は発症から6時間以内という制約がありましたが,時間的制約が緩和され,より末梢の血管まで適応が拡大し,恩恵を受けられる患者が増えています。しかし,閉塞血管が再開通しても脳梗塞となり症状が改善しない場合など,治療のメリットがどの程度あるのか疑問に感じることがあります。実践面で注意すべきことなど,診療のコツを教えていただけると幸いです。
神戸市立医療センター中央市民病院・太田剛史先生にご解説をお願いします。
【質問者】

山田茂樹 滋賀医科大学脳神経外科学講座病院講師
【回答】
【対象患者の適切な選択と専門医の確保が重要である】
2015年のpivotal studies以降,脳血栓回収療法は拡大の一途をたどっています。特に最終健常確認時間から6時間以内の内頸動脈,中大脳動脈近位部閉塞では必須の治療です。とはいえ,適応が拡大すると同時に実践面で注意すべきことも増えています。
第一に,最終健常確認時間から6時間以上の場合です。「脳卒中治療ガイドライン2021」では16〜24時間以内でも推奨度A〜Bが与えられています。もととなった研究では全自動の急性期脳梗塞・灌流評価ソフトであるRAPIDにより適応が判断されていましたが,RAPIDは日本では普及しておらず,症例ごとに適応を慎重に検討する必要があります。しかし,FLAIR(fluid-attenuated inversion recovery)はtissue clockとなりうる,という報告1)もあり,今後はMRI画像での診断が根拠となるかもしれません。

残り1,052文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する