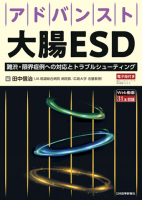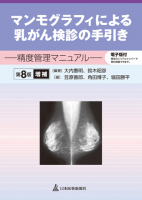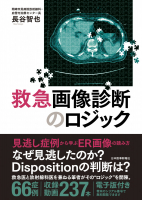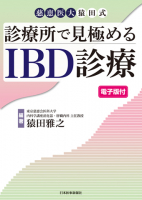お知らせ
fusion imagingの現状と今後の活用について

腹部超音波では造影,elastographyなどによる診断技術が著しく向上しています。さらにCTやMRIなどの他の画像診断modalityを活用しfusionさせることにより,教育,診断,治療に大いに活用されることが期待されています。
このfusion imagingの分野において革新的なアイデアで新しい手法を開拓し,教育,診断,治療に活用されているトップリーダーの1人である高松赤十字病院・小川 力先生にfusion imagingの現状と今後の活用についてご教示をお願いします。
【質問者】

廣岡昌史 愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学/総合診療サポートセンター准教授
【回答】
【必要不可欠なtechnology。ナビゲーションやシミュレーションとの融合に注目】
専門分野でない人では,超音波検査におけるfusion機能をご存じでない人もいるかもしれないため,最初にfusionについて簡単に説明させて頂きます。
fusionとは,CTやMRIなどの他の画像modalityのdigital imaging and communications in medicine(DICOM)dataを超音波装置に取り込み,超音波検査前に1分ほどの位置合わせを行います。それにより超音波装置の画面に,通常の超音波検査の画面に加え,プローブの動きに同期した同一断面のCTやMRIの画面があらゆる断面で表示されるtechnologyで,各社の主な上位機種の超音波装置に装備されています。
このtechnologyは2003年に日立アロカメディカル(現日立ヘルスケア・マニュファクチャリング)により開発されていますが,その後各超音波装置メーカーから開発されています。fusion systemの呼び方はRVS,V-NAV,Smart Fusion等各社により名称は違いますが,大まかな原理はほぼ同じです。現在では通常の超音波検査では同定,確信が困難な小さな結節の診断や,ラジオ波焼灼術(radiofrequency ablation:RFA)などの補助として日常診療で用いられています。

残り817文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する