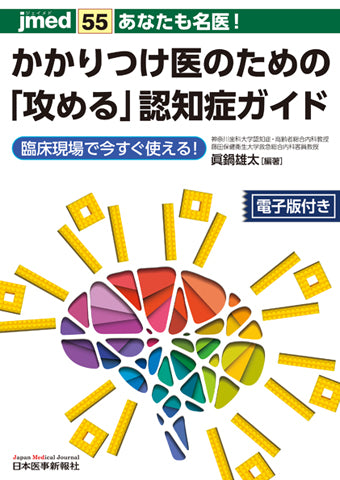jmedmook55
あなたも名医!かかりつけ医のための 「攻める」認知症ガイド【電子版付】
臨床現場で今すぐ使える
これ1冊あれば大丈夫!認知症を”識る”ための知識を網羅的に紹介!
目次
第1章 認知症を“識る”
1とんでもない時代がやってきた!-日本の現状と世界
2認知症とは?
3認知症の中核症状
4認知症に伴う行動異常と精神症状
5認知症を診断するために必要な問診・診察手技・検査
6認知症を診断するための神経心理学検査-総論
7認知症を診断するための神経心理検査-外来で使える応用編
8認知症を診断するためのMRI-疾患ごとの読影ポイント
9認知症を診断するためのSPECT/PET-疾患ごとの読影ポイント
10認知症を診断するためのバイオマーカー検査
第2章 認知症を原因疾患別に“識る”
1アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)
2脳血管障害(脳血管性認知症)
3レビー小体病(パーキンソン病,レビー小体型認知症)
4前頭側頭葉変性症
5その他のパーキンソニズムを伴う認知症
6正常圧水頭症
7嗜銀顆粒性認知症,辺縁系神経原線維変化性認知症
8糖尿病,肝性脳症,ビタミンB12欠乏症,甲状腺機能低下症
第3章 認知症の治療を症状別に“識る”
1アセチルコリンエステラーゼ阻害薬-総論,使い分け,切り替え法
2非選択的NMDA受容体遮断薬(メマンチン)-総論,具体的な処方例
3抗パーキンソン病薬-L-dopa製剤を中心に,具体的な処方例
4抑肝散,抑肝散加陳皮半夏-総論,具体的な処方例
5BPSDの治療-総論
6易怒,興奮,暴力行為の治療-アルツハイマー型認知症を中心に
7幻覚の治療-レビー小体型認知症を中心に
8妄想の治療-疾患による違いと成因背景,対応,具体的な処方例
9うつ症状の治療-無為との違い,治療法,精神科へ紹介すべき症例
10睡眠障害の治療-具体的な薬剤選択
11意識明晰度の動揺(日中傾眠),せん妄の治療
第4章 認知症の予防・介護・在宅医療・法律を“識る”
1軽度認知障害-定義,診断基準を中心に“予備軍”を理解する
2サルコペニア,フレイル-認知症予防のための基礎知識
3健康生活-食事・飲酒・運動・睡眠から見る具体的な認知症予防
4口腔ケア-歯と歯周病からみる認知症予防
5BPSDへの対応-具体的な対応・指導例
6認知症患者のリスクマネジメント-ケースでみる具体的な指導
7在宅介護のサポート体制-患者にあった介護環境,具体的な指導法
8介護保険-求められる主治医意見書,内容を具体的に教えます
9介護家族のメンタルケア-かかりつけ医にできること,すべきこと
10認知症に関わる遺伝要因-正しく質問に答えるためのHow to
11在宅医療-概要と連携の実際
12終末期対応-認知症患者のIVH,胃瘻,介護者への説明の仕方
13認知症医療と法律-運転免許証,成年後見制度
序文
巻頭言
認知症患者,推計462万人。日常臨床にあって,診療科を問わず「認知症」と相対さなければならない時代です。“地域のかかりつけ”として活躍されている先生方であればなおさら,「私は専門じゃないから」と逃げられないのではないでしょうか。拍車をかけるように,2015年1月27日には国策としての認知症施策推進総合戦略,いわゆる「新オレンジプラン」も策定されました。国家の意思として,医師,歯科医師,薬剤師,看護師といった医療者すべてに「認知症」への理解を深め,啓発活動に参加することが希求されているわけです。「認知症」は,従前の神経内科医や精神科医が担当していればよいという専門的な疾患から,医療者である以上,誰であろうとある程度の対応ができて当然な, むしろ対応しなければならないcommon diseaseへ変質したと言えるでしょう。
こうした時代の要請に応え,日本認知症学会や日本老年精神医学会,日本老年医学会など関連学会による専門医の育成や日本医師会による認知症サポート医の育成は勿論,専門医による非専門の先生方への啓発活動,各種学習書籍の出版など,様々な取り組みがなされています。とはいえ,後者に関しては専門的な内容でありすぎたり,具体的な解決策の明示に欠いた,帯に短し襷に長し的な内容のものが多いと感じていらっしゃる向きも多いのではないでしょうか。
本書は,臨床場面で必ず相対さなければならない「認知症」に関し,今すぐ使える,より実践的な「認知症ガイドブック」を編集の方針としております。疾患,治療,介護,法律など,先生方が特に知りたいと思われる内容を項目立て,その分野の第一線において活躍されている著名な先生方に執筆を担当して頂きました。各項の内容に関しても,evidenceに基づきつつ,一方でこれのみにとらわれることなく患者や介護者へのアドバイスの仕方など,実践的な内容を意識して執筆して頂いております。
本書を手にした先生方におかれましては,認知症診療における必携の書として,日々の診療にご活用頂ければ幸いです。
神奈川歯科大学認知症・高齢者総合内科教授/藤田保健衛生大学救急総合内科客員教授 眞鍋雄太