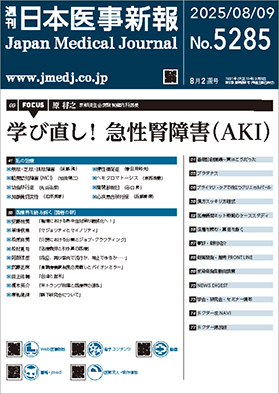お知らせ
【識者の眼】「医業経営と5つの前提」松原由美
No.5280 (2025年07月05日発行) P.59
松原由美 (早稲田大学人間科学学術院人間科学部教授)
登録日: 2025-05-08
最終更新日: 2025-05-07
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
医業経営は、一般産業の経営と異なるのか、という質問を受けることがある。筆者はいつも半分YESで半分NOと答えている。経営戦略、財務管理、組織管理、マーケティングなど、マネジメントの手法はほとんど同じと言えよう。しかし、前提がまったく異なる。
第一に、医業経営は人の生命や障がい、生活に密接にかかわる。一般産業でも、たとえば鉄道事故をはじめ事故が起きれば生命にかかわるが、医業経営は事故でなくても生命にかかわる。

第二に、医業経営は生命や障がい、生活にかかわるため、社会性、公益性が高い。
第三に、第二の理由から、社会連帯の思想をベースに制度(国民皆保険制度、社会保障制度)が設計されている。言い換えれば、お互い様の考えをベースとした制度で成り立っている。支払い能力ではなく、ニーズに応じてサービスが提供される制度設計と言える。これに対して、一般産業は市場経済にゆだねられているため、支払い能力がない者は購入できなくてよいという前提が成立している。筆者の息子が保育園児のころ、「フェラーリがほしい」と言っていたが、支払い能力がないため、わが家では今も昔も自転車に乗っている。
第四に、第三の理由から、税や公的社会保険料といった広い意味での公的資金でその事業費が賄われている。
第五に、第四の理由から、サービスを利用していない者からも強制的に事業費を負担させる仕組みとなっている。
上記の前提は、医業経営の特質でもある。第一の特質は、医療そのものの特質だが、第二の特質は当該社会の価値観、または社会規範による。そして第三〜第五の特質は、当該社会の価値観や規範に基づき人為的につくられた制度である。人為的な制度(国民皆保険制度)は人為的に壊すことが可能だ。制度を壊すことは簡単だが、再構築することはきわめて難しい。また、制度は最終的に政治が決めるが、政治は世論の影響を受ける。つまり、私たち一人ひとりが、どのような社会を善しとするのか、価値観が試される。
公的保険の制度維持が限界であるため、民間保険を活用すべきという声がある。しかし、民間保険は魔法の杖ではない。民間保険は医療ニーズがある者ほど加入できない、または保険料が高くなり加入しづらいなどといった特質があり、公的保険の代替はできない。公的保険が正常に機能してこそ、民間保険による社会全体のウェルビーイング向上が可能となると言えよう。
医療が支払い能力ではなく、ニーズに応じて受けられる制度を維持することは、人生のスタートラインである生命が平等である社会を守り、社会の分断を緩和し、社会不安の波の防波堤となる。
制度の維持には制度への信頼と財源が欠かせない。物価上昇分を医療費に反映させなければ、働き手の確保はできず医療の持続的な提供はできない。医療の持続的な提供には、税や保険料による地域住民や企業の負担が不可欠といえる。そして負担を強いる以上、医療提供側にも国にも説明責任を果たす義務がある。また、昨今ホスピスホームにおける不正請求が社会問題となったが、質の高い医療を効率的に提供する地道な実践とたゆまぬ努力が求められる。
医業経営では、この医療という社会的共通資本を守る姿勢が求められる点が、一般産業の経営との大きな差だと筆者は考える。
松原由美(早稲田大学人間科学学術院人間科学部教授)[医業経営][社会連帯][社会的共通資本]