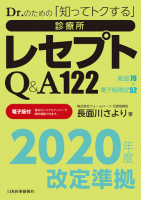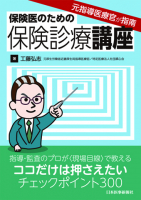お知らせ
【識者の眼】「健康診断を再考せよ」岩田健太郎
岩田健太郎 (神戸大学医学研究科感染治療学分野教授)
登録日: 2025-08-07
最終更新日: 2025-08-05
先日、健康診断を受けた。無駄が多い。たとえば心電図(ECG)。基礎疾患も症状もない成人に、毎年心電図をとるメリットはどのくらいあるのだろうか。
心血管系のヘルス・メンテナンスにおいて、推奨されるのは定期的な血圧の測定、血糖やヘモグロビンA1cを用いた糖尿病のスクリーニング、脂質プロファイルの測定、そして喫煙経験者の腹部超音波検査(腹部大動脈瘤のスクリーニングのためだ)などだ1)。

発作性心房細動(PAF)の検出のために、スマートウォッチなどを活用するのは興味深い方法だが2)、年1回のECGで、PAFが偶然検出される可能性は低い。「やった感」を醸し出しているだけではないのか。
同様に「やった感」を醸し出しているだけなのは、身体診察である。短時間でポンポンポンと胸に聴診器を当てるだけで、無症状の成人の何人に、異常所見を見出すことが可能なのか。ちなみに私を診察した高齢医師は、腰をかがめて私の腎臓のある位置に聴診器を当てていた。どんな音が聞こえたのかは、知らない。
古くから、がん検診はエビデンス・ベースで行うことが大事とされてきた。ここでの「エビデンス」とは、「アウトカムが出せる」ということであり、アウトカムとは、たとえば全死亡のような臨床的に意味があるアウトカムだ。「がんが見つかることもある」だけではダメなのだ。
健康診断を擁護する人は、「いやいや、ときどきこういう異常所見が見つかることもある」と言うのだが、「見つける」だけではダメなのだ。
かつて、私は小学校の学校健診もエビデンスを欠くと批判した。この議論も感情的になりがちだが、メリットとデメリットの理性的な吟味が必要である。
社会保障費が高額化して、支払側の、特に若者世代の不公平感は強くなっている。社会保障は大事だが、無尽蔵にお金を出せと言われても多くは理解、納得しないだろう。高額療養費制度の自己負担増加や、処方薬の市販薬化といった議論がなされるのは当然だ。であるならば、せめてメリットのほとんどないところから、メスを入れるのが合理的な判断というものだろう。
厚生労働省は、労働安全衛生法とその運用基準を見直し、エビデンスに基づいた合理的な検査内容に改めるべきだ。もちろん、この問題は利益相反が絡んでおり、関係諸氏は猛反対するだろう。しかし、人口減少の現代において、金銭的、人的リソースの無駄遣いが許されるはずがない。
本丸の国民皆保険制度を死守するためにも、無駄の削除は必然なのである。
【文献】
1)Schattner A:Am J Med. 2024;137(8):706-11.
2)Senoo K:J Arrhythm. 2025;41(4):e70143.
岩田健太郎(神戸大学医学研究科感染治療学分野教授)[健康診断]