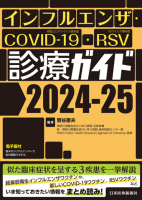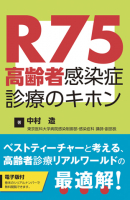お知らせ
【識者の眼】「新型コロナウイルス:地域の医療機関での話し合いと中国の方に受診方法をわかりやすく」和田耕冶
新型コロナウイルスは、今のところ感染症法において対象になっていません。そういうこともあってか、地域においてどこの医療機関が(例えば感染症指定医療機関など)対応するかといったことも決められていないようです。
重症急性呼吸器症候群(SARS)の時は、2003年4月に新感染症(人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状または治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの)になりました。その後、ウイルスが特定された同年6月に指定感染症(定義一部省略:当該疾病のまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの)になり、同年11月5日より感染症法の改正に伴い、第一類感染症(現在は二類)としての報告が義務づけられるようになりました。

新型コロナウイルスに関しては、こうした法的な手続きには時期尚早ということもあるのでしょう。しかし、法令による動きがないこともあってか、自治体などでの対応が十分になされないことが実感されています。皆さんの地域ではどうでしょうか?
自治体や国が主導して受診方法の情報提供を
中国からたくさんの観光客が来ていますが、新型コロナウイルスの拡大に備えて、もし具合が悪くなったらどこに受診したら良いかの誘導もそろそろする時期ではないかと感じています。特に、中国語の通訳となると人材が不足しています。春節ですから、中国からの留学生は中国に帰国して、アルバイトも不足となっています。
自治体や国が主導して、①中国語での医療機関の受診方法、②症状がある場合の咳エチケット、③事前の電話の後の受診(なかなか言葉ができないと難しいが)─などの情報提供をすることはできているでしょうか。検疫の強化がよく話題になっているようですが、潜伏期間の限界を考慮すると、こちらの方が重要と考えます。
また、中国語による受診や具合が悪い場合の相談体制を構築できないでしょうか。かつて新型インフルエンザが流行した時に受診にあたって電話相談を自治体が実施しましたが、すぐにパンクしたことは考慮すべきです。
最近AIによるチャットなどもあるようですが、そうしたものでできないものでしょうか。きっと東京五輪・パラリンピックの際にも役立つ経験になると思います。
(著者注:2020年1月23日早朝の情報をもとにしています)
和田耕冶(国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授)[新型コロナウイルス②]