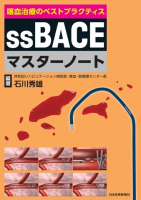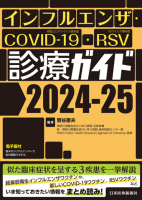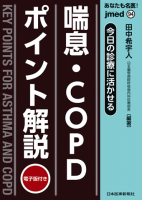お知らせ
増加する非結核抗酸菌(NTM)症の疫学的現状とその背景について
近年増加する,非結核抗酸菌(nontuberculous mycobacteria:NTM)症の疫学的現状とその背景について,ご教示下さい。結核予防会複十字病院・森本耕三先生にご回答をお願いします。
【質問者】

工藤翔二 結核予防会理事長
【回答】
【わが国は肺NTM症の高蔓延状態にあることが明らかとなった】
NTMとは結核以外の培養可能な抗酸菌であり,自然環境のみならず水道,風呂場などの家庭環境にも広く分布しています。長い間NTMは環境雑菌(弱毒菌)として捉えられていましたが,1980年代頃より呼吸器臨床医は,NTMによる肺感染症(肺NTM症)の増加を実感していました。しかし,その臨床的負担の増加にもかかわらず,結核と異なり基本となる疫学情報を欠いていたために,その重要性を示すことができませんでした。また,2000年以降,既に専門病院以外でも患者数が増加し,その対策が求められるようになりましたが,一般的認知度も低く,その状況は変わることはありませんでした。
近年,この状況が変わり,肺NTM症対策の機運が高まった大きな要因は,日本医療研究開発機構(Japan Agency for Medical Research and Development:AMED)支援による研究班(阿戸班)が多角的疫学調査を行い,その実態を示したことによります。2014年に行われた全国アンケート調査では,罹患率(同年の新規症例数/10万人)が14.7/10万人と,菌陽性結核のそれを初めて超えたことを示しました。この結果はEmerging Infectious Disease1)へ報告され,メディアでも広く取り上げられることとなりました。

残り993文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する