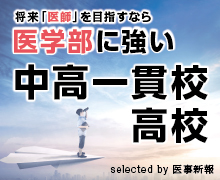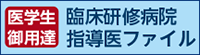お知らせ
特集:完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)の仕組み
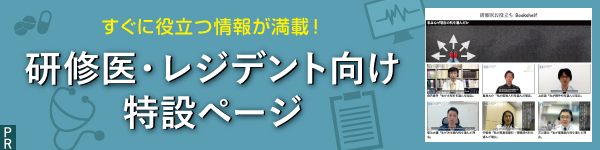
監修:栗田隆志(近畿大学病院心臓血管センター教授)
■監修のことば
経静脈的に植込むICD(経静脈ICD)の最大の問題はリードによる血管障害,感染した場合の細菌播種や困難なリード抜去であり,これらは,皮下ポケットに留置した本体と経静脈リードが物理的に接続されているという,数十年来,恒常的であった基本的デザインに起因する。リードと本体すべてのシステムを皮下に植込むSubcutaneous ICD(S-ICD)はこれらの問題を解決する切り札として考案された画期的なデバイスである。2016年にわが国でもS-ICDが臨床使用可能になり,致死的不整脈発生リスクを持つ多くの患者にとって新たな選択肢が増えることになった。ただし,リードが直接心臓に接触していないため,T波や心外ノイズによる過剰感知と不適切作動の懸念,徐脈ペーシングや抗頻拍ペーシングができないこと,除細動閾値が高くなること,などが問題として残されている。また,これまでの経静脈ICDとは異なる植込み法や設定法が行われるため,手術手技や術前後の管理について医療従事者の高い習熟度が求められる。
今回のS-ICD特集では,本機器の構造から術後管理に至るまで,わが国のエキスパートによる解説を頂戴することができた。S-ICDに関する正しい認識と適正な使用を広げることが本特集の目的であり,新たな治療法の展開を知るための絶好の機会として頂ければ幸いである。

■目次
1 S-ICDに備わった機能と植込み法
西井伸洋(岡山大学病院医歯薬学総合研究科先端循環器治療学講座講師)
2 S-ICDの利点から見た適応・不適応例
佐々木真吾(弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座准教授)
3 S-ICD留置後の問題と今後の展開─車の運転制限も含めて
丸山将広(近畿大学医学部循環器内科学)