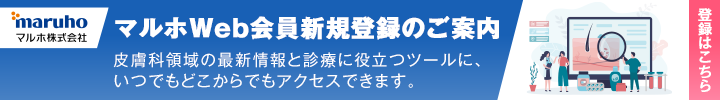1816年に発表された『日本幽囚記』(井上満訳、岩波書店)には、ロシアの軍艦ディアナ号の艦長ヴァシリー・ゴローニン(1776~1831)が、1811年に国後島で松前藩の警備兵に捕縛された後、松前や箱館で約2年3カ月監禁されていた当時のことが描かれている。その中で、精神医学的に興味深いのは、監禁中に「発狂した」ムール士官に関わる記述である。
ムールは、自分がロシアに関する情報を日本側に漏らしたことが祖国にばれれば帰国後重罪に問われるのではないかと心配していたが、1813年3月頃から次のような異常な言動が見られるようになる。
1)「日本の役人たちがこの家の屋根に登って、お前はなぜ日本の米を食い、日本の血をすするのかと大声で僕を責めます」とか、「毎晩通詞たちがやって来てゴロヴニンやフレーブニコフとひそひそと僕を殺す相談をします」といった幻聴や被害妄想を思わせる「狂人のような話」を始めた。
2)ゴローニンが「ムール君はいつも半ば気の狂った人間のような話し方をして、私の質問には全然関係のないような、ちぐはぐな返事をする」と言うような疎通性の障害を感じさせる言動が出現した。
3)松前から待遇の好い箱館に移される時も、1人だけ「両眼に涙を浮べ、その後も道中でたびたび泣いていた」。日本側はムールの自殺を恐れて厳重に見張っていたが、「皆があんなに喜んでいるのに、あなただけそんなに涙を流すのはどういう訳ですか」と尋ねると、「僕には日本側からこんなお情けを受ける資格がないと感じたからです」と自責的・自罰的な答えをした。
4)その一方で、「日本側は陰険狡猾で、きっと皆を殺すに違いない」「日本側の張りめぐらした網について、露艦に警告する」というような被害妄想的な面もあったため、ゴローニンはムールには「一種の発狂状態に襲われる瞬間がある」と考えている。
5)箱館で解放されてディアナ号に乗り込んだ時、士官たちは大喜びでゴローニンたちを抱擁したが、ムールだけはじっと立ちつくしていた。「彼は自分のいる場所も、その時の出来事も、少しも判らない様子だった」。
6)ムールは「絶えず良心に苛まれ」、ゴローニンに持ってきた報告書には「私は売国奴で、裏切者です」と記されていた。しかも、「この報告は文に脈絡もなく、訳も判らぬ囈語が入っていたので、ムール君は全く理性を失っていることが明白に判った」という。
7)その後ムールは回復し、「半狂人のような話振りをやめて、昔の通り非常に立派な態度」で話すようになったため、ロシア人には悪いことをしたのでカムチャダール族と一緒に暮らしたいというムール本人の要望を容れることにした。それまで何度か自殺未遂を繰り返していたムールも「すっかり別人のようになっていた」からだが、その矢先、ムールは看視役の従卒が目を離したすきに猟銃で自らの心臓を打ち抜いて自殺した。1813年11月22日、30歳になる直前だった。
このように見てくると、ムールには、幻聴や被害妄想を思わせる症状のほか、疎通性の悪さや思考障害などの統合失調症的な症状が認められる。しかし、その一方で、抑うつ的な気分変調や自責・自罰感、涙もろさ、自殺企図などがあり、およそ8カ月の病期の後、状態が改善して周囲が油断した隙に自殺したことも含めてうつ病的な特徴も認められる。そのため、限られた情報からの推測ではあるが非定型精神病もしくは統合失調感情障害的な病だった可能性もある。
しかし、もう1つ『日本幽囚記』で注目されるのは、そうした精神変調を来したムールへの周囲の対応である。
そもそもゴローニンは、ムールの発狂を「良心と善良な感情を持った人が、ムール君のように数奇な、気の毒な運命に弄ばれて、一時の迷いで正道を離れた」と心因反応的に捉えている。また、ムールがロシア側から見れば裏切り的な行為をしたことについても、「ムール君の行状を厳しく責めないでほしい」「これを通読されたら読者はこの不幸な士官に対して憎悪を感じないで、却って同情同感の涙を流されるであろう」と擁護するなど、ムールに対しては終始、共感的な立場に立っている。
実際、ムールが監禁中に自分がとった行状がロシアで咎められるのではないかと心配した時も、ゴローニンは「君の罪は君自身で考えているほど恐ろしいものではない。われわれは昔のことは努めて、すっかり忘れることにした」「現在君は良心の苛責に悩んでいるが、将来功績を立てればその良心も鎮まるであろう」と言って慰撫しているが、いくらゴローニンが「心配せずに安心し給へ」と言っても何の効果もなかったという。さらに、本人の希望を容れてカムチャダール族と過ごせばこれまでのことを思い出したり気持ちを搔き乱すことに触れずにすむだろうと考えるなど─結果的には無効に終わったものの─、ゴローニンは最後までムールを見捨てることなく自殺予防に努めるとともに、何とかしてその理由なき不安を払拭し、安心させようと努力している。
その背景には、ムールがかつて5年間ゴローニンとともにディアナ号に乗り組んでいた時には、「ムール君は珍らしい才能を持った士官で、職務に必要な各般の学識があるうえに、各国語に通じ、絵画はきわめて巧みであった。彼は職務を愛し、これに全魂を打ちこみ、誠心誠意職責を果していた。彼と交際した者は誰でも彼を気持のよい快活な社交家と思っていた」と評価されていたことも影響していようが、それに加えて日本側の通訳もムールに同情的な態度をとっていることは興味深い。特に貞助という通訳はムールに対して、「日本の官職に就きたいと願い出たことは、大して悪いことではないでしょう。皆さんが絶望に陥ったために、そうした行動が生れたのだから」と慰めつつ、「あんたがお奉行様の小使を志願しているということは、僕は皆に打ち明けていないし、又そんなことは僕として打明けるに忍びなかったのです」「あんたの生命にかかわるようなことは政府に知らせはしないと思います」といった通訳の枠を超えた配慮までしている。
貞助は、江戸時代後期、異国の精神障害者に対しても好意的な態度を示した人間として我が国が誇りとすべき人物なのである。