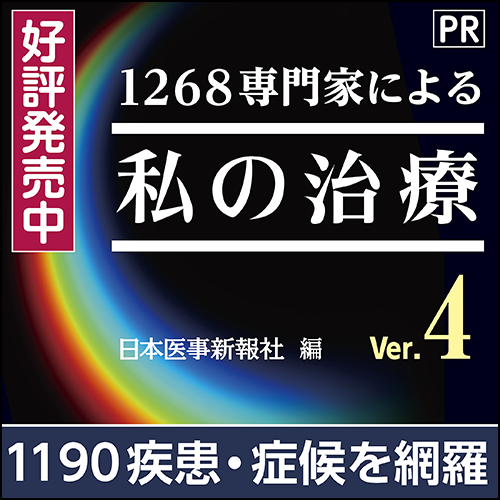閉経後骨粗鬆症は,閉経以降の女性の骨粗鬆症であり原発性骨粗鬆症に分類される。閉経によりエストロゲンが減少することで破骨細胞が活性化し,骨破壊が亢進し,高回転性の骨粗鬆症が生じる。閉経期以降の女性の4人に1人が閉経後骨粗鬆症と報告されている。
▶診断のポイント
周閉経期の女性には,子宮癌・乳癌検診と併せて骨密度検査を骨粗鬆症のスクリーニングとして勧める。骨密度検査では,椎体と大腿骨近位部の両者を測定することが望ましい。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
椎体および大腿骨近位部の骨密度検査,FRAXⓇを施行し,原発性骨粗鬆症の診断基準1)に合致する場合は,薬物治療を開始する。薬剤の使用の有無に関係なく,閉経前後の女性に対しては,「骨を強くする食事」と「骨を強くする運動」を指導することは大切である。
薬剤としては,エストロゲンの欠乏が骨粗鬆症の原因であることを考慮するとホルモン補充療法(HRT)が挙げられ,産婦人科としては注目するが,不正出血や処方禁忌,慎重投与の症例もある。そのため,HRTは第一選択薬とはならないが,産婦人科へコンサルトしながらの使用については検討の余地がある。産婦人科としては,骨粗鬆症を主体にHRTを施行することは少なく,更年期障害の治療の一環として骨密度の改善をめざし,他の骨粗鬆症治療薬を併用する場合も多い。
HRT以外の治療法として,一般的には早期の閉経後骨粗鬆症には,選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)を,高齢者または椎体および大腿骨近位部骨折抑制を目的とした骨粗鬆症には,ビスホスホネート製剤,抗RANKL抗体薬,副甲状腺ホルモン薬を選択する。カルシウムバランスが負の状態にある患者には,カルシウム製剤,活性型ビタミンD3製剤の投与を併せて選択されることも多い。
骨粗鬆症治療の効果は,定期的な骨密度検査,骨代謝マーカーで判定し,これらの結果を考慮して薬剤を選択する。