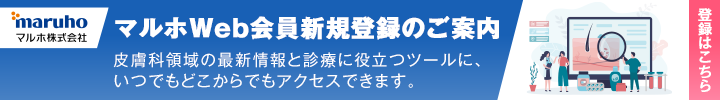TOP > jmed 79 最新知見を現場に活かす! 誤嚥性肺炎 治療と予防の新常識 > 1章 総論 2.誤嚥性肺炎薬物治療
×
絞り込み:
124件
カテゴリー
診療科
コーナー
解説文、目次
シリーズ