お知らせ
福島原発事故から5年 国際専門家会議から見えてきたもの─[OPINION :福島リポート(22)]
- 登録日:
- 2018-05-10
- 最終更新日:
- 2018-05-10
東日本大震災、そして直後の福島第一原発事故という複合災害から5年が経過した。初期の混乱と混迷の中で被災住民への対応の様々な課題も明らかになり、“現存被ばく状況”(被ばく線量が平常時の公衆の線量限度(1mSv/年)より高い状態が定着し、さらなる線量低減に長期間を要する状態)と呼ばれる放射能汚染問題との関わり方も、その理解や認識の違いによる各自の行動変化として現れてきている。長引く避難生活での困難な状況や精神心理的なストレスは続くが、それでも徐々に冷静な判断と行動が可能となりつつある。
一方で、福島県の農林水産物に対する風評被害も続き、原発事故を契機に地域住民の分断や差別、偏見も報告され、震災関連死や自殺の増加も現実視される。これらの事象に対して、当初から専門家が発し続けている放射線リスクの本質について考察する。
専門家の拠り所
原発事故直後からのクライシスコミュニケーションと、復興に向けた放射線リスクコミュニケーションの最前線に立たされた時の拠り所は、国際的なコンセンサスが得られている放射線防護基準となる。
私の場合は、原子力放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)や国際放射線防護委員会(ICRP)などの科学的考察と政策提言ガイドライン、世界保健機関(WHO)や国際原子力機関(IAEA)のコンセンサス、そしてチェルノブイリ笹川医療協力事業で20年間にわたり現場を歩いた原子力災害対応の経験であった。特に、広島・長崎における長年の晩発性放射線障害の調査研究と、事故前の国内外の緊急被ばく医療ネットワーク準備状況は、想定外の事象に対してもクライシスの現場では重要な判断材料であり行動の拠り所であった。
しかし、理論と実践のギャップを痛感したのは、まさに専門家の落とし穴とも言うべき己自身の情報伝達力の稚拙さと、情報受信者の千差万別なリスク認知の違い、そして話の真意が正反対に取られるような解釈の違いに曝されたときであった。当初の情報不足からマスコミの過熱報道の渦中に身を置き、ソーシャルネットワークを介した正誤の確認がないまま氾濫する放射能や放射線に関する誤った情報に対しての防御や訂正の術を持ち合わせることなく、専門家が徒手空拳で現場対応に奔走することを余儀なくされた。クライシス対応の課題と反省である。
事故直後の専門家の現場活動
地震、津波、そして原発事故に遭遇した福島県の医療の最後の砦は、福島県立医大と附属病院であり、非常事態のなか、救命救急医療、患者搬送やトリアージなどで自衛隊、消防、警察や県職員らと共に献身的な活躍をした。しかし、原発事故対応では、日本の原発安全神話という虚構の中で医療関係者さえも浮き足立った。さらに公衆被ばく対応が後手後手となり、被災住民は政府・東電に対する不信と不満、怒りが募り、生活インフラの崩壊と相まって、放射能恐怖との闘いの上で困難な避難生活を余儀なくされた。事態の収拾が見えない中での放射線健康リスクと社会リスクへの対応は、少数の専門家による集団リスク対応に終始するばかりで、きめ細やかな個人リスクへの対応や対話集会は困難であった。単にクライシス時のガバナンス問題だけではなく、放射線防護文化も全体に未成熟であった。
以上のような原子力災害に伴う混乱や混迷を、国内の専門家の努力だけで沈静化することには限界があり、2011年9月11、12日に第1回国際専門家会議「放射線と健康リスク」(日本財団主催)が福島県立医大で開催された(図1上)。UNSCEAR、WHO、IAEA、ICRP、米国放射線防護測定審議会(NCRP)、さらにチェルノブイリ原発事故関係者など30名近い海外の専門家が出席し、事故に関する解析所見と客観的な評価、そして調査についての提言が初めて取りまとめられた。会議後の3時間近い記者会見では多くの質疑応答があった。今提言を読み直しても中立性と不動性が際立つ権威ある内容であり、ここに概要を再掲する。

国際専門家会議の提言
(1)福島の原発事故は大きな複合災害により発災した。それにもかかわらず、住民の避難や水道水・食料対策は適切に実施された。今日まで、原発事故による急性放射線障害は発生していない。ヨード剤による甲状腺ブロックは住民に対して原則施行されず、結果としても甲状腺被ばく線量は低かったと報告されている。これらの事象に加えて、報告されている環境放射能汚染レベルを考慮に入れると、放射線被ばくによる住民への直接的な身体的健康影響は限られており、チェルノブイリに比べても非常に小さいと考えられる。チェルノブイリでは唯一甲状腺がんのみが証明されている。しかしながら、この事故の社会的、精神的、そして経済的な影響は、福島でも甚大であり、今後も継続すると考えられる。継続したこれらへの影響についての配慮が望まれる。住民が元の場所に安全に帰ることができ、様々な問題について正確な情報に裏打ちされた決定ができるようなモニタリングと評価が必要である。
(2)医療専門家は、福島県民へ最大限の支援を提供するために、常に最新のエビデンスを入手する必要がある。すなわち、継続的な健康モニタリングと調査事業が必要であり、その第一歩は必要な情報を収集することから始まる。福島県民健康管理調査事業の初期段階の計画が本シンポジウムで紹介され、是認された。その結果、調査事業の回収率向上を図るためには、住民の声を反映できるよう組織された地域参加型の事業展開が不可欠と考えられる。
(3)過去60年の長きにわたり、広島と長崎の被爆者への医師や科学者による医療支援と研究を通じて、日本は世界でも最高の放射線に関する経験や知識を有している。この専門知識は福島原発事故の被災住民に還元すべきであり、同時に得られた情報から最大限学ぶ責任を持たなければならない。
(4)日本は最先端の緊急被ばく医療対応システムを有しているが、今回の放射線災害は、そのシステムが依存していた地域インフラの破壊を伴う複合災害の結果発生した。十分なコミュニケーションと既存の医療サービスは、必ずしも十分には提供されなかった。今回の教訓は検証され、問題点が解決される必要がある。
(5)医療専門家と科学者は、放射線の影響についての理解促進に努め、現在の情報をできるだけ分かりやすく福島県内外の住民に理解してもらうよう心がけるべきである。そのためのリスク評価と意志決定には透明性が肝要である。同時に、科学的エビデンスとその解釈については、一般の人々に対して分かりやすい言葉で提供される必要がある。
(6)すべての医療サービスの中に、社会的、心理的な支援の準備が組み込まれ、さらなる住民への貢献が必要とされる。
(7)ICRP、WHO、IAEA、UNSCEARなどの機関による長期にわたる国際的な支援が重要であり、国際機関の間でも協力関係の強化が必要である。
(8)日本政府と国際機関は、長期的な協力関係を効果的に継続するために、この災害から学んだことをいかに最大限活用できるかの課題を解決すべきである。1つの方法は、政府と地方自治体、そして利害関係者、国際機関などからなる福島原発事故に関するタスクフォースの組織化に着手することである。その役割は、現在進行中、あるいは将来の福島で計画される種々の国内および国際的なプロジェクトの調整や、一連の管理者や専門家の会議を組織し、それらを通して、事故から起こされる放射線による環境影響と健康影響について「信頼のおける専門家の統一見解」の取りまとめ、さらに環境改善と特別なヘルスケア・プログラムについての助言と、必要な新たな研究分野についての提言などである。
国際機関が果たした役割
以上の提言を受けて、福島県民健康管理調査事業(現在は健康調査事業)が福島県立医大を実施責任機関として継続され多くのデータが蓄積されている。この間、国内では各種の事故調査委員会が早い時期に報告書を出したが、健康影響の評価は時期尚早でもあり、評価に資するデータも収集されていない。その中で13年、WHOはいち早く、予備的な被災住民の被ばく線量評価から福島における放射線健康リスクを推定している。予防原則の観点から実際の被ばく線量を過大に評価したものであり、より安全対策に立脚した報告書となっている。一方、14年に出されたUNSCEAR2013年報告書と、15年のIAEA報告書は、その後のデータも加味され、優れた専門家による科学的解析が行われており、内容は格段と充実している(図2)。しかし、放射線被ばくによる健康影響面では線量推計の不確実性を考慮し、特に初期の放射性ヨウ素内部被ばくによる甲状腺がんリスクについては慎重な内容となっている。また、精神心理的な影響による二次健康影響を危惧した内容であり、その結論に沿った対応策がすでに福島県でも相談員制度などで開始されている。
これらの基礎資料になっているのは福島の現場からの精度管理された調査報告書であり、一般住民のみならず原発作業者の放射線リスクについても検討が加えられている。国際機関の専門家は、当初の勧告から現在に至るまで福島への支援を緩めることなく、特にICRPは生活回復を目指し住民と対話する「ダイアログセミナー」を継続開催し、UNSCEARは報告書の概説を県内外で紹介している。
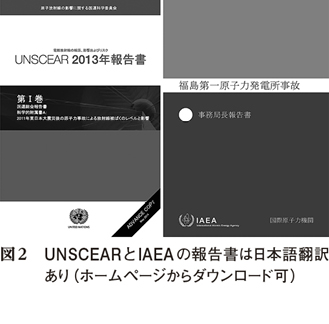
今後の展開
原発事故半年後に開催された第1回国際専門家会議では、優れた海外専門家の陣容から的確に当時の状況が分析された。ここでの提言は県民の健康見守り事業推進の原点として肝に銘じる必要がある。その後も会議は継続的に開催され、14年の第3回会議では復興における医療関係者の役割を中心に、首相への直接提言という形で勧告された(図1下)。
県民健康調査事業は種々の課題を抱えながらも現在進行形である。特に、甲状腺超音波検査の導入による大規模調査では、思春期前後からの小児・若年者甲状腺がんの診断数が問題となり、一部論争の的になっている。これらの問題でも現場目線でのきめ細かな住民対応の継続が必要であると同時に、国際社会における専門家のコンセンサスが重要となる。さらに理解や判断の拠り所を専門家だけではなく、被災住民とも共有した検査結果の解釈や説明が求められ、長期にわたる健康見守り事業を、科学的データの蓄積と解析から推進する必要がある。
最後に、チェルノブイリ原発事故から30年、その経験と教訓は国内外の専門家によって共有され、福島県で生かされている。その結果、福島県立医大の「ふくしま国際医療科学センター」を中核として、災害・被ばく医療科学の各種人材育成事業と共同研究、そして原子力災害対策に資する全国横断的な取組みが始動した。福島の復興を健康面から支えるふくしま国際医療科学センターの充実が期待される。


長崎大理事・副学長/福島県立医大副学長(非常勤) 山下俊一(やました しゅんいち)
1978年長崎大卒。90年同大原研教授。内分泌・甲状腺、放射線医療科学専攻。2005年WHO放射線専門科学官、09年長崎大医歯薬学研究科長、11年福島県立医大副学長。13年から長崎大理事・副学長。内閣官房原子力災害専門家、日本学術会議会員



























