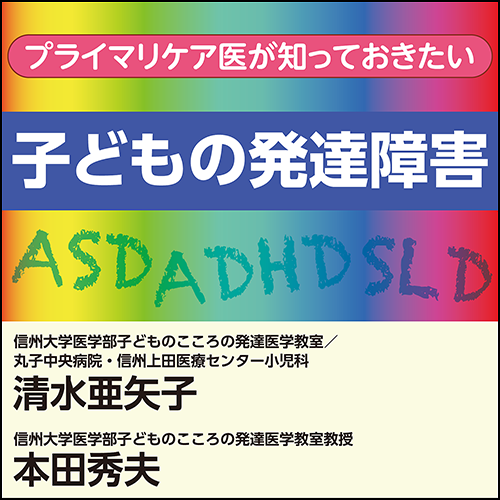プライマリケア医が知っておきたい子どもの発達障害
一般外来での発達障害診療の入門書
PDFとHTMLの両方で読めるハイブリッド版です。
ネットショップ「STORES. jp」の弊社ストアjmedj.netで購入できます。
本文はログイン状態で御覧ください。
●執筆
清水亜矢子(信州大学医学部子どものこころの発達医学教室/丸子中央病院・信州上田医療センター小児科)
本田秀夫(信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授)
●商品説明
判型:A4判
頁数:23頁
発行日:2022年10月26日
990円(税込)
※本商品は「週刊 日本医事新報」5129号の特集を再構成したものです
●内容紹介
▷発達障害の概念が広まり、一般外来においても発達障害に関する質問や相談を受けることは珍しくなりました。確定診断は一般外来では困難であるものの、プライマリケア医が発達特性について説明したり養育環境について助言を行ったりすることで、保護者など周囲の人の理解が深まり、より適切な対応を促すことができます。
▷そこで本コンテンツでは、プライマリケア医が知っておきたい主な発達障害として、「自閉スペクトラム症(ASD)」「注意欠如・多動症(ADHD)」「限局性学習症(SLD)」「コミュニケーション症群」の特性について解説。さらに、様々な困難を抱える本人と、育てにくさを感じる保護者への助言を障害ごとにまとめました。
▷例えば、音への過敏性があるASDの子どもには「我慢させるのではなくイヤーマフや耳栓を使用する」、順序立てて実行することが困難なADHDの子どもには「言葉ではなく、いつでも確認できる“見える目安”、視覚的補助を用いる」など、現時点での困り事に対して具体的な助言を提示します。
▷ケースによっては、発達障害診療医とプライマリケア医が連携して行う継続的な薬物療法が、社会適応や生活のしやすさにつながることから、最近使用される代表的な薬剤についても概説しました。
▷著者は、成長過程にある子どもにおいて信頼関係のあるプライマリケア医の存在は「必要不可欠」と期待します。個々の特性を見据えた医療支援を一般外来で行う際の入門書として、本コンテンツをご活用ください。
【目次】
1.主な発達障害の特性と,状態に応じた保護者への助言
(1)自閉スペクトラム症(ASD)
(2)注意欠如・多動症(ADHD)
(3)限局性学習症(SLD)
(4)コミュニケーション症群
2.薬物療法と,よくある併存疾患
(1)非定型向精神薬
(2)注意欠如・多動症(ADHD)治療薬
(3)睡眠障害の薬剤
(4)漢方薬
(5)併存疾患と,よくある生活上の困り感
3.信頼されるかかりつけ医になるために
日本医事新報社のWebオリジナルコンテンツ(PDF+HTMLのハイブリッド版)です。
購入いただくと、①ダウンロード式でどこでも読めるPDF版と、②シリアルナンバー登録で利用できスマホでも読みやすいHTML版(別途通信が必要です)の両方が利用できます。
HTML版の利用に当たっては、初回のみ弊社サイトでのシリアルナンバー登録が必要となります(弊社サイト有料会員の方は特に手続きは必要ありません)
※シリアルナンバーは商品購入後、3営業日以内にご登録のメールアドレスへ配信されます(小社営業日:祝日・年末年始を除く月~金曜日)。
シリアルナンバーの登録・利用方法は下記をご参照ください。
https://www.jmedj.co.jp/premium/DLM/DLMS/