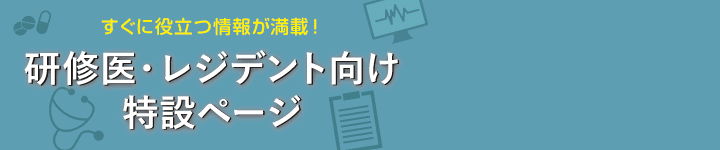お知らせ
Ⅳ期肺癌に対する外科の役割 【分子標的薬の出現により,再生検の意義が見直され,長期生存が得られる例も】

肺癌に対する根治的切除術の適応は今も変わらず,肺内と一部の局所リンパ節に腫瘍が限局し,かつ全摘出ができる症例に限定される。一方,Ⅳ期肺癌とは遠隔臓器転移もしくは胸腔内播種を伴う状態であり,当然根治的な切除の意義はない。しかし,分子標的薬の発達に伴い,このような進行肺癌もしくは再発肺癌に対する外科の新たな役割が見直されている。
分子標的薬の使用に際しては,腫瘍の持つ特定の遺伝子変異もしくは分子学的特質を知る必要があり,進行癌では腫瘍の一部を生体組織診断(生検)することで情報を得る。しかし,肺癌は1つの腫瘍内部においてですら多様性に富むことが知られており,微小な生検検体で腫瘍全体の情報を得ることは困難である。一方,EGFR遺伝子変異を有する腫瘍に対するチロシンキナーゼ阻害薬も一定の奏効期間の後,ほぼ全例が耐性を獲得することが知られている。耐性の獲得には,T790M遺伝子変異などいくつかの機序が明らかとなっており,またこれも腫瘍間で必ずしも同一ではない。
したがって,1人の症例に対して分子標的薬を使用した場合でも,個々の腫瘍で効果の程度や再燃の有無が異なっていることが多い。このような状況において,効果の乏しい腫瘍を外科的に摘出することで,腫瘍の持つ分子学的特質の全貌や耐性の機序を知ることができ,かつ長期生存が得られる症例も報告(文献1)されている。有効な薬剤が開発されることで外科の役割もまた変わりつつある。
【文献】
1) Mitsudomi T, et al:Nat Rev Clin Oncol. 2013;10(4):235-44.