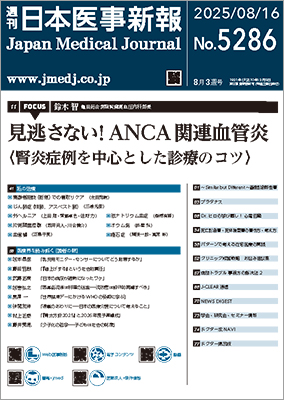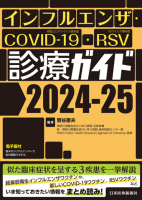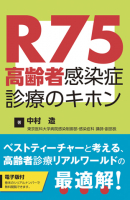お知らせ
オウム病[私の治療]

オウム病は細胞内増殖菌であるオウム病クラミジア(Chlamydia psittaci)による人獣共通感染症である。主として感染したトリやその排泄物に含まれるC. psittaciを吸入することで感染する。口移しでの餌やりや噛まれて感染することもある。C. psittaciは乾燥状態でも長期にわたり感染力をもつため,トリに直接接触しなくても,トリの排泄物よりオウム病に罹患することがある。潜伏期間は1〜2週間で,軽症から重症まで様々な病像を呈する。原因不明の重症肺炎では本症を鑑別疾患に入れる必要がある。感染症法では全数把握疾患の4類感染症に指定されている。
▶診断のポイント
オウム病に特有の症状はない。発熱,咳嗽(通常は乾性咳嗽),呼吸困難等の呼吸器症状のほか,頭痛や筋肉痛,消化器症状,神経症状など呼吸器以外の症状を呈することもある。胸部画像所見では大葉性肺炎から気管支肺炎パターンなど多様である。胸部CTでは周囲にすりガラス陰影を伴う結節影がみられることもある。血液検査では特異所見は知られていないが,白血球増多は認めないことが多く,トランスアミナーゼの上昇がみられる症例もある。

診断のポイントとして鳥類との接触歴を確認する必要があるが,飼育鳥が死んでいる場合には特に疑いが強い。一方で,C. psittaciを保菌していても外見上異常を認めないトリも知られている。トリを飼育していなくても,トリの糞への曝露によって感染したと考えられる事例もあるため,住居や職場へのトリの飛来や,巣をつくっていないかということ,ペットショップへの訪問歴等を確認する必要がある。
鳥類との接触歴のある患者の臨床症状から本症を疑う。βラクタム系薬が有効でないことも診断の手がかりとなる。一般の医療施設では診断が困難で,保健所や地方衛生研究所に検査を依頼する必要がある。咽頭ぬぐい液や喀痰,血液検体からの分離・同定による病原体の検出や,PCR法による遺伝子の検出,血清の抗体検出により診断する。市販のマルチプレックスPCRの検出対象にC. psittaciは含まれていない。オウム病の発症頻度は高くはないが,鳥類との接触歴があり,本症が疑われる場合には検査を依頼することが重要である。

残り965文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する