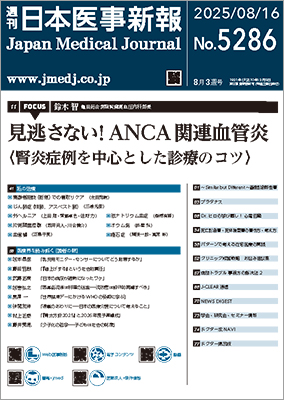お知らせ
【識者の眼】「経験値主義」田上佑輔
No.5280 (2025年07月05日発行) P.61
田上佑輔 (医療法人社団やまと理事長、やまと在宅診療所院長)
登録日: 2025-05-14
最終更新日: 2025-05-13
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
とある場所で年に一度、人と異なる才能を誇る優秀な若者のプレゼンを聞くという贅沢な仕事を6年以上続けている。1日中缶詰で、1日12人程度、日本や米国、欧州、アジアまで、10歳代の子ども達のプレゼンを聞く。不思議なことに、参加者が増えているのか、セレクションの基準が変わってきているのか、年々選抜される彼らのプレゼンが似てきているような気がする。
過去には幼少期からある微生物に興味を持ち、微生物同士が非接触で互いを認識していることに気づき、研究を始めるような、他との違いを感じさせる子どももいた。しかし、最近の書類選考を抜けてきた子どもたちは皆、甲乙をつけづらいくらい優秀で、何でもよくできる。なぜ自分が彼らの話を聞いているのか理解できなくなるくらいだ。10歳代なのに、AIやビッグデータ研究から複数のプロジェクトを掛け持ちし、論文を書き、起業し、ボランティア活動、芸術まで、素晴らしい経験をしていて申し分ない。学校が終わると何も考えず外で遊び、部活に明け暮れていた自分を振り返ると、隔世の感がある。

ただ、日本と海外のプレゼンを比較して聞いていると、世代や時代の問題でもなく、今の日本の子ども達でもこうしたプロジェクトや学業以外の経験値が圧倒的に少なく、機会の違いを感じる。海外では大学進学のためのコンサルタントがついて、経験値を積ませる文化があり、この差は当然といえる。同席していた大学教授の話では、日本では修士の学生でも2年間で論文を書くのが大変で、そもそも研究にあてるリソースが違いすぎ、外部の若者に論文を書かせる余裕がないと話す。この時点で経験値教育のシステムそのものに差が生じている。
本質的には、日本の受験システムから生まれた早い時期からの塾通いと同様に、海外の経験値主義も大学受験に必要とされる基準に合わせて子どものために用意された教育という点では変わりはないという見方もある。そこで表現される個人の自主性や創造性が、社会に出てから通用するものかどうかは未知数だ。ただ、グローバルな優秀スタンダードが早期からの多様な経験値とされるなら、筆記試験重視の日本教育は大きなハンデを抱えているというのは明確な事実だ。用意された経験値だけが優秀さではないと理解しながらも、そこに惑わされずその人自身を評価できるかはわからない。
医師という職業にも同様の点が指摘されている。少子化にもかかわらず、医学部受験倍率は上昇している。しかし、筆記試験で優秀な人が必ずしも医師に適しているとは限らない。多様な経験をしているほうがまだよいのかも不明である。さらに、今回感じたように、教育における個性や多様性を重要視して、多様性を追求すればするほど、皮肉なことに「多様性」を強調した新たな均質化が進む側面もある。むしろテストの点数だけで評価するほうが、自然なゆらぎを生み出すことがあるかもしれないという逆説的な発想。この均質化からどう抜け出すか、あるいは抜け出す必要があるのか。教育現場の外野から見ている筆者としては次のパラダイムシフトが訪れるのが楽しみであり、今後の医師のあり方にも関係すると考えている。
田上佑輔(医療法人社団やまと理事長、やまと在宅診療所院長)[多様性][経験値]