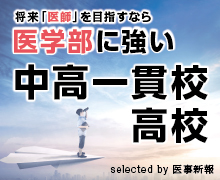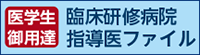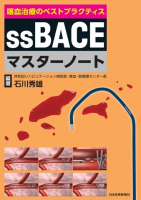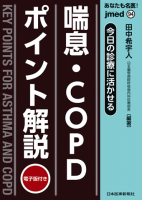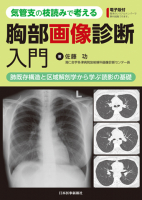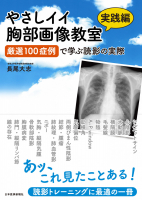お知らせ
睡眠時無呼吸症候群[私の治療]
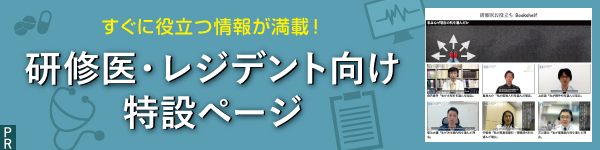
睡眠時無呼吸症候群(sleep apnea syndrome:SAS)は,睡眠中に無呼吸が繰り返されることにより生じる症状や,無呼吸に起因する様々な合併症を起こす症候群である。睡眠時無呼吸には,上気道の虚脱により生じ呼吸努力を伴う閉塞性と,呼吸中枢や神経・筋などの障害による呼吸努力を伴わない中枢性がある。特に閉塞性睡眠時無呼吸(obstructive sleep apnea:OSA)患者の頻度は高く,成人男性の約20%,閉経後女性の約9%との最近の疫学調査もある。
▶診断のポイント
頻度の高い疾患で,肥満・眠気といった典型的な患者像にとらわれてはいけない。むしろ患者により病態・病像は異なり,症状(いびき,眠気,夜間頻尿,倦怠感など),背景リスク(肥満,小顎・短頸,高齢など),合併症(高血圧,不整脈,心不全,糖尿病,脳卒中など),呼吸器疾患〔咳,喘息,慢性閉塞性肺疾患(COPD)など〕など,いろいろな角度から本疾患を疑い,疑えば検査をすることが重要である。

▶私の治療方針・処方の組み立て方
中等症以上のOSAの第一選択治療は,持続気道陽圧(CPAP)療法である。保険適用は脳波を含む睡眠検査で無呼吸低呼吸指数(AHI)20以上,簡易検査で40以上である。CPAPの有効性のエビデンスは豊富であり,基準を満たせば,積極的に導入を試みるべきである。従来は,「眠気などの症状やQOLの改善」が主な治療目的であったが,現在は,「将来の心血管障害予防も含めた生命予後の改善」も同時に重要であるとされる。リスク因子を考慮した合併症も含めた全身的な観点から,治療管理を施していく必要がある。
CPAP基準を満たさないOSAやCPAP不耐の場合,口腔内装置(OA)の適応である。近年,CPAP継続困難な患者に舌下神経電気刺激療法が承認され,今後の展開が注目される。
中枢性睡眠時無呼吸(CSA)の場合,その発生に寄与する基礎疾患(心不全など)の治療を適正化することを優先し,またそれ自体が治療になる。それでもCSAが残存する場合,CPAP,酸素療法,adaptive servo ventilation(ASV)などを考慮する。

残り1,039文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する