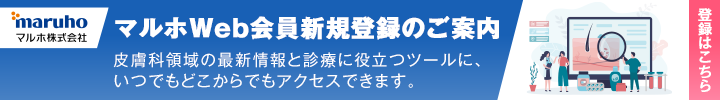1980年代の終わり、国立横浜病院(現:国立病院機構横浜医療センター)の外科医だった筆者は、家庭医療を学ぶために米国ニューヨーク・ブルックリンへ留学した。厚生省(当時)国立病院課の臨床研修指導医海外留学制度によるものである。この制度は、日本医師会会長であった武見太郎氏が「米国のプライマリ・ケアに学ぶべきだ」と提唱したことをきっかけに始まった。
留学先は、ブルックリンの中心部、黒人街やユダヤ人街が混在するクラークソン通りにあるニューヨーク州立大学ダウンステート医療センターの家庭医療科(ファミリー・プラクティス)だった。
午前中はファミリー・プラクティスの外来センターで診療を担当した。わからないことがあると、会議室でパイプをくわえ、新聞を悠然と読んでいる年配の指導医である開業医に質問しながら患者を診た。心強い存在だったのがナース・プラクティショナーの看護師たち、そしてフィジシャン・アシスタント(PA)と呼ばれる医療助手である。外来センターには小さな検査室も併設されており、外来検査を手伝ってくれた。さらにソーシャルワーカーの支援も欠かせなかった。
何よりの味方は、ファミリー・プラクティスのレジデントたちだった。彼らは世界各国から集まっており、ドイツ人のエッカート、ハンガリー人のポールのほか、イタリア、メキシコ、プエルトリコ出身のレジデントもいた。エッカートは「日本とドイツは歴史的に親友だ」といつも語り、ポールはかつてのオーストリア=ハンガリー帝国の栄華を誇らしげに話した。チーフレジデントのミリアムの早口ニューヨーク英語には、ずいぶんと戸惑わされたものだ。
彼らとともに、関連病院でのローテーション研修も行った。通りを挟んだキングスカウンティ病院や、精神科のキングスボロ病院などである。キングスカウンティ病院の救急外来(ER)には2カ月参加したが、テレビドラマさながらの目まぐるしさだった。12時間シフトが瞬く間に過ぎていく。当時はエイズの流行期でカリニ肺炎、トキソプラズマ脳炎、粟粒結核、クリプトコッカス髄膜炎など、日本ではほとんど経験できない日和見感染症を次々に目にした。カポジ肉腫にも遭遇し、聴診をしようとした患者の前胸部一面に母指頭大のワインレッド色の斑点が広がっているのを見て、言葉を失ったことを覚えている。
冬のニューヨークは雪が多い。雪道に足を取られながら、病院から病院へと移動したローテーションの日々が、今では懐かしい。こうして2年間の留学を終え、日本へ帰国した。
ところが帰国後、思いがけない現実に直面した。日本医師会が、厚生省による当時の家庭医構想に強く反対していたのである。1987年の「家庭医に関する懇談会」報告書に対しても、大きな反発が起きていた。そのような逆風の中では、「米国で家庭医療を学んできました」と胸を張って言うことができなかった。こうして、筆者の家庭医としての歩みは、厳しい逆風の中で始まったのである。
武藤正樹(社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ理事)[家庭医療][プライマリ・ケア]