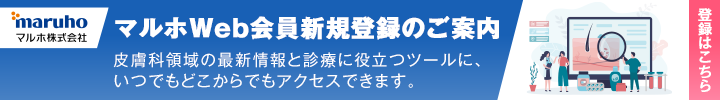2024年の診療報酬改定で新設された「地域包括医療病棟」は、2025年11月時点で220病院・1万1383床にまで広がった(リンク参照)。地域包括医療病棟は、高齢の救急患者を受け入れ、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援などを包括的に提供し、在宅復帰につなげる機能を評価した病棟である。
では、この病棟がどのような経緯で生まれたのかを改めて振り返りたい。近年、75歳以上の高齢者救急は増加の一途をたどっている。こうした患者を受け入れる病棟について最初に議論されたのは、2014年の診療報酬改定で新設された「地域包括ケア病棟」の検討時である。この議論を行ったのは中医協総会の下部組織である入院医療分科会(現在の入院・外来医療等の調査・評価分科会の前身)で、当時筆者はこの分科会の座長を務めていた。
地域包括ケア病棟には、「ポストアキュート機能」「サブアキュート機能」「在宅復帰支援機能」の3つが位置づけられた。ポストアキュート機能は、急性期治療が一段落した患者の受け入れを担い、サブアキュート機能は高齢者の軽症〜中等度の救急患者を受け入れる機能を指す。
この「高齢者救急」を地域包括ケア病棟で扱うべきかどうかが、分科会で最も議論を呼んだ点だった。地域包括ケア病棟の看護配置は13対1が基本であるため、「この人員配置では高齢者救急は対応しきれない」という反対意見が多かった。その中で、入院医療分科会委員の1人だった武久洋三氏(当時、日本慢性期医療協会会長)は、自らが経営する博愛記念病院(徳島県)でも高齢者救急を受け入れている例を示し、「慢性期病院でも対応しているのだから、地域包括ケア病棟でも可能だ」と述べた。こうした経緯から、高齢者救急を地域包括ケア病棟の機能として位置づけることになった。
しかし、この案を中医協総会で報告した際には、大きな反発が起こった。「入院医療分科会が越権行為をした」とまで批判されたほどだ。最終的には高齢者救急を受け入れる方向で決着したものの制度開始後の実態をみると、週7日受け入れていた病棟がおよそ60%あった一方で、まったく受け入れていない病棟も13%存在した。やはり看護配置13対1の枠組みでは、高齢者救急の受け入れには無理があったと言える。
この課題をふまえ、看護配置10対1の「地域包括医療病棟」が新たに設けられた。これが現在、全国に広がっている病棟の源流である。
制度創設の過程では、こうした紆余曲折はめずらしいことではない。しかし、中医協総会の場で、診療側と支払い側の委員が忌憚なく意見を交わすことは、制度の成熟に欠かせないプロセスだ。苦労も多かった当時の議論だが、今思えば、診療報酬改定前年の秋の中医協総会での論争は懐かしさすら覚える。
武藤正樹(社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ理事)[地域包括ケア病棟][地域包括医療病棟][診療報酬改定]