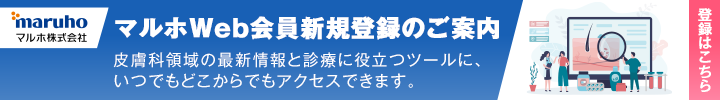1990年6月、1989年の合計特殊出生率が1.57まで低下したことを受け、「1.57ショック」と呼ばれる衝撃が走った。忌避された「丙午」の1966年(合計特殊出生率1.58)を下回り、戦後最低の水準が記録されたことから、国はこの年を契機に少子化対策を本格化させた。しかし、それから30年以上が経過した2024年、合計特殊出生率は1.15にまで落ち込み、出生数は初めて70万人を割り込んだ。「出生数68万人ショック」との表現が報道各社で相次ぎ、1990年は今や“出生率が高かった時代”とみなされるようになっている。
女性外科医にとっても、育児とキャリアの両立はいまだ高いハードルである。家事・育児の主な担い手であり、配偶者の47.5%は常勤医師である。一方、男性外科医の配偶者の65.5%は専業主婦である1)。育児環境の非対称性は働き方にも反映されており、子どもを持つ男性外科医の93.1%が常勤勤務であるのに対し、女性は72.0%にとどまっている2)。非常勤の立場では、執刀や責任ある業務を担うことが難しく、本人の意向とは無関係にキャリアの第一線から退かざるをえない。
では、制度が整い、配偶者の協力もある環境であればそれを乗り越えられるのか。筆者自身の経験は、そう簡単ではないことを示している。当時の勤務先は「日本一子育て支援制度が整っている」と称された病院であった。だが実際には、「24時間365日働くのが外科医」という考えが根強く、体力が続く限り、仕事と家庭を両立しながら走り続ける、出口の見えない耐久レースのような日々が続いた。実は第二子を望んでいた。ところが第一子でさえ綱渡りの状況であり、第二子を出産すればその時点で外科医としてのキャリアが終わることは明白であった。夫は「僕は1人でも十分だ」と言い、第二子を断念した。
子どもが小学校高学年を迎えたころ、子育て支援制度を離脱し、独身時代と同様の働き方をした。ただ、家事・育児との両立による慢性的な疲弊が積み重なり、体調を崩し倒れた。仕事と家事の二重負担は、独身時代より明らかに過酷であった。
さらに、子どもが高校生になると、夫に転勤の辞令が出た。ようやく仕事に打ち込めると期待していた矢先に新たな試練が降りかかり、呆然とするほかなかった。
出産や子育てを契機に生じるこうした構造的な負荷は、女性医師のキャリアに「見えにくいペナルティ」として作用し続けている。その現実はいまだ十分に是正されていない。一般的に少子化の背景として結婚観・家庭観の多様化、経済的不安定や将来不安など様々な要因が挙げられるが、医師の共働き世帯においては、長時間労働と性別役割の固定といった構造的・文化的障壁が出産・育児の大きなブレーキとなっている。こうした障壁が取り払われない限り、出産や育児は依然として「個人の選択と努力」にゆだねられたままであり、多くの女性が静かにキャリアを諦めることになる。
【文献】
1) Kawase K, et al:Surg Today. 2018;48(3):308-19.
2) Kawase K, et al:Surg Today. 2018;48(1):33-43.
河野恵美子(大阪医科薬科大学一般・消化器外科)[外科医][キャリア]