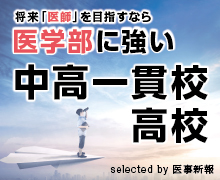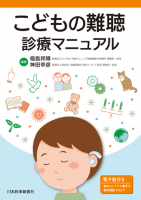お知らせ
アレルギー性鼻炎[私の治療]
アレルギー性鼻炎は発作性反復性のくしゃみ,水様性鼻漏,鼻閉を三主徴とする。耳鼻咽喉科医とその家族を対象とした有病率調査の結果1)2)では,1998年は29.8%,2008年は39.4%,2019年は49.2%と有病率が上昇しており,季節性アレルギー性鼻炎である花粉症,その中でも特にスギ花粉症で有病率の上昇が認められている。また2019年の結果からは小児におけるスギ花粉症の有病率が上昇しており,低年齢化が認められている。一方,一年を通して症状を呈する通年性アレルギー性鼻炎では有病率の上昇は認められていない。アレルギー性鼻炎は重症化することで,QOLや労働生産性の低下をきたすことが知られている。さらに気管支喘息を合併することがあり,合併疾患と連携した治療が求められる。
▶診断のポイント
「鼻アレルギー診療ガイドライン2024年版」1)に記載されている診断と治療の流れでは,症状,病歴,治療歴などの問診を行ったあとに,鼻腔内所見を確認して下鼻甲介粘膜腫脹および水様性鼻漏の分泌量を確認できれば,アレルギー性鼻炎と診断できるとしている。このような所見が認められない場合,治療を行ったあとに十分な治療効果を得られない場合,あるいはアレルゲン免疫療法を開始する場合は,皮膚テストや血清特異的IgE検査などの抗原同定検査を行い確定診断とする。鑑別疾患として,感染性鼻炎や老人性鼻炎,あるいは妊娠性鼻炎などの非アレルギー性鼻炎が挙げられる。


残り2,685文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する