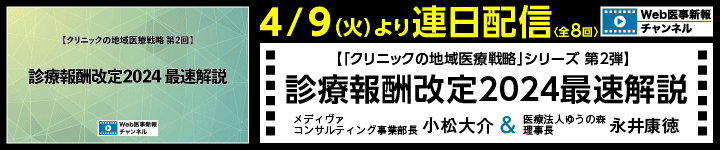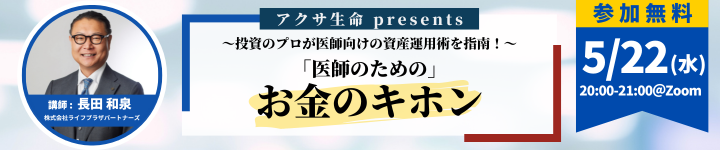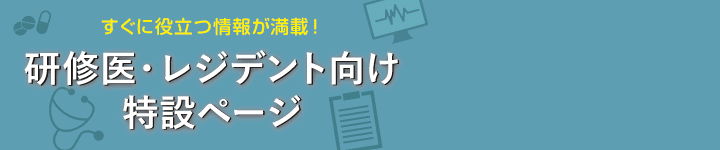お知らせ
司馬遼太郎の『胡蝶の夢』─続・文学にみる医師像[エッセイ]
1979(昭和54)年に司馬遼太郎が発表した『胡蝶の夢』(新潮社刊)には、幕末の混乱期、関寛斎という当代を代表する蘭方医が「心疾」、すなわち心の病に取り組んだ様子が描かれている。
1862(文久2)年に阿波・蜂須賀家の侍医となった寛斎は、藩主・斉裕の診察をすることになるが、1863(文久3)年、初老の斉裕を診た寛斎の印象は、「なんと暗い人だ」というものだった。実際、当時の斉裕については、「神経を病んでいるらしく、ほとんどひきこもりがち」「つねに鬱懐があり、いつみても泣きっ面をしている」「いつも目を伏せ、目を伏せると、両眼のあたりが薄墨で刷いたようにくらい翳ができた」「神経の障害のために朝ちょっと表御殿へ出て、すぐ奥御殿にひっこんでしまう」「精神の沈鬱がはなはだしく、食欲がまったくなく、不眠がつづき、ときに小児のように条理をうしなう」などの記述があるため、抑鬱的な状態にあったことは間違いない。
ところが、司馬は鬱病説をとらず、「こんにちでいえばノイローゼの昂じたもの」としているほか、当時は寛斎以外の漢方の侍医たちも、「しもじもでいう気ままということで、病いではない」と思っていたため、毒にも薬にもならない漢方の薬が投薬されていた。
鬱病という病がきちんと認識されていなかった当時、大名でさえそのつらさが理解されず、まともな治療がなされていなかった様子がうかがえるが、寛斎はそうした当時の医学の限界と医師の振舞いを、「漢方にせよ蘭方にせよ、医学が癒せる病気の数はたかが知れたもので、だからといって医者はじっとしているわけにもゆかず、わかったような顔つきで患者と社交しているようなものだ」と喝破する一方で、斉裕の病については彼なりの考えがないでもなかった。
寛斎の本音は「恋わずらいと同じで、一種の心疾だから、大名を廃めてしまえばなおる」というもので、その背景には佐幕か勤王かで揺れていた当時の緊迫した政治情勢があると、心因論的な観点から寛斎は斉裕の病を次のようにみている。「寛斎は、斉裕の病気が時勢病であると見ている。時勢に対して阿波徳島藩をどう持ってゆくかということについて、処理能力をうしなった。まじめで気の小さい男だけに、表御殿(執務所)へゆくことがこわくなり、穴に首だけ突っこんでいるように奥で逃避し、病気と称している」。
ただ、寛斎の特徴はそうした斉裕の逃避性や無能性を認識しつつも、斉裕に対する愛情を失っていないことで、司馬遼太郎は、「寛斎は斉裕に人間としての愛情を感じていた」「政治への把握能力をうしなったために極度の神経衰弱になり、無気力のまま生きている斉裕に対して寛斎が人間的な愛情を感じていたことはたしか」などと記している。
おそらくここに、寛斎が優れた臨床家たりえた秘密の一端が示されているのであって、寛斎は長崎でポンペから学んだ「医者はよるべなき病者の友である」という教えの忠実な実践者だったのである。