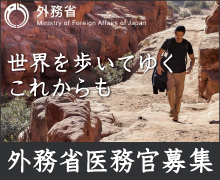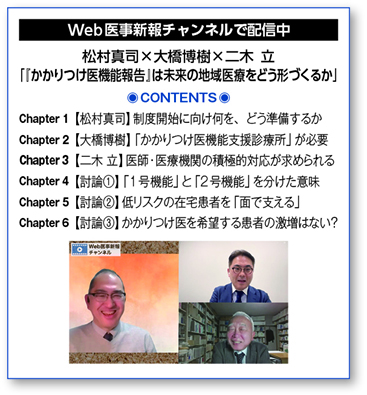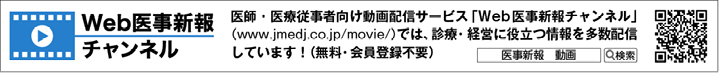お知らせ
[Web医事新報チャンネル]「かかりつけ医機能報告」は未来の地域医療をどう形づくるか【シリーズ・クリニックの地域医療戦略】(松村真司×大橋博樹×二木 立)
医師・医療従事者向け動画配信サービス「Web医事新報チャンネル」では、クリニックの地域医療戦略シリーズ第4弾「『かかりつけ医機能報告』は未来の地域医療をどう形づくるか」(全6回)を2月27日より無料で公開しています。本動画には、プライマリ・ケアの立場から松村真司氏(松村医院院長)と大橋博樹氏(多摩ファミリークリニック院長/日本プライマリ・ケア連合学会副理事長)、医療政策の研究者の立場から二木立氏(日本福祉大学名誉教授)が出演。かかりつけ医機能報告制度(2025年4月施行)が地域医療に与える影響、クリニックが取るべき対応について、それぞれプレゼンした上で討論を繰り広げています。本欄では討論の見どころをダイジェストで紹介します。(動画は1月15日に収録しました)

松村 真司 (まつむら しんじ)
松村医院院長
1991年北海道大学医学部卒。UCLA総合内科・公衆衛生大学院、東大医学教育国際協力研究センターなどを経て、2001年より現職。専門は総合診療とプライマリ・ケア。編著書に『プライマリ』『外来診療ドリル』『帰してはいけない外来患者』(いずれも医学書院)など。

大橋 博樹 (おおはし ひろき)
多摩ファミリークリニック院長
2000年獨協医科大学卒。川崎市立多摩病院総合診療科医長などを経て、2010年多摩ファミリークリニック開業。日本プライマリ・ケア連合学会副理事長。東京医科歯科大学臨床教授。聖マリアンナ医科大学臨床教授。共著に『若手院長です 開業のこと何でも質問してください』(プリメド社)など。

二木 立 (にき りゅう)
日本福祉大学 名誉教授
1972年東京医科歯科大学卒。代々木病院リハビリテーション科科長・病棟医療部長、日本福祉大学教授・副学長、学長を歴任。専門は医療経済・政策学。著書に『病院の将来とかかりつけ医機能』(勁草書房)など。日本医事新報誌上で「深層を読む・真相を解く」連載中。
1号機能と2号機能に分けたのは画期的
松村 大橋先生は分科会(=厚生労働省「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」)の議論に関わっていましたが、かかりつけ医機能を「1号機能」(日常的な診療を総合的・継続的に行う機能)と「2号機能」(時間外診療、入退院支援、在宅医療、介護等との連携などの機能)に分けて規定したのは非常に画期的なアイデアではないかと思います。分科会ではどのような議論があったのでしょうか。
大橋 1号機能は、主に患者・市民から見て、何か症状があるときに、地域のどの先生が診てくれるのかを探しやすくするにはどうすればいいかというシンプルな問いから始まりました。「症状」がいいのか「領域」がいいのかなど突っ込んだ議論がありましたが、結果として「診療領域+よくある疾患」に落ち着きました。
一方、時間外対応、入退院支援、在宅医療など、医療提供側としてどのように地域を支えていくかを考えるための議論の道具、資料も必要ということで、(2号機能では)それらを把握することになりました。
二木 私は1号機能と2号機能の基準が全然違うことが大事だと思っています。1号機能は各医療機関・医師が持っているか否か。それに対して2号機能は、医療機関・医師が直接できなくても「連携」でカバーすればいい。ここが全然違うんです。
かかりつけ医機能の議論で最初の頃は「かかりつけ医が24時間、在宅も全部すべきだ」という意見もありましたが、それは完全に否定されました。そんなことは不可能ですよね。2号機能は「面として支える」ということだから、自院と他の病院・診療所、介護施設などとの連携で提供すればいい。逆に言うと、この制度を活かして、今まで独立型だったところもできるだけ連携することが求められてくると思います。
日本の診療所は独自に発展した
松村 二木先生は各国の医療調査にも携わり長年研究されてきたということで、1号機能と2号機能を分けたことを評価されていますが、「かかりつけ医機能」を海外に発信する場合、英語でどのように表現すればいいでしょうか。
二木 一番曖昧な言葉で“Family Doctor”がいいと思いますよ。
英国もドイツもフランスも、かかりつけ医、主治医制度があるかどうかは別にして、診療所の医師はごく一部の専門医を除けば最初から一般医として養成されているわけです。逆に言うと、診療所で手に負えない人はみんな病院に行ってしまう。
それに対して日本の診療所は、先生たちのような総合診療医もいますが、多くの医師は臓器別の専門医を持って開業し、患者の必要に応じてプライマリ・ケアのいろいろな機能を持つようになっていきます。
これはあまり知られていないのですが、日本の診療所はものすごく重装備なんです。英国、ドイツ、フランスの診療所は看護師だってまともにいない。日本の医師は「かかりつけ医機能+ある程度の専門性」を持っていて、職員もたくさんいます。診療所ができる診療の枠が欧米の診療所に比べて広く、レベルも高いわけです。それは誇っていいことだし、逆に言うと米国や欧州と単純には比べられない。日本の診療所は独自に発展したということを踏まえて考えるべきだと思います。
かかりつけ医を希望する患者の激増はない
松村 二木先生は(制度の施行で)かかりつけ医を求める住民が激増して混乱が生じることはないと予測していますが、その理由をお聞かせいただけますか。
二木 日本国民全体で見ると、かかりつけ医を持っていると本人が判断している国民あるいは患者は5割程度しかいないのですが、患者の中心である高齢者に限定するとすでに8割ぐらいはいるんです。これが1つ。
2つ目は、よく「コロナ禍でかかりつけ医を持つことが必要という国民が増えた」と言われますが、日医総研の調査を見ると、コロナ禍の前後で「かかりつけ医を持っている」と回答している人は増えていない。働き盛りの健康な人、年に1、2回程度しか医療機関を受診しない人はわざわざかかりつけ医を持とうとは思わないと思います。
3つ目は、日本人は「信頼」で動いていますから、(かかりつけ医機能として提供する医療の内容について)杓子定規で「お医者さん、書いてください」と言う患者さんは多くない。ドイツはかかりつけ医の制度はなくても患者の9割がかかりつけ医を持っている国ですが、ほとんどが契約ではなくて日本と同じ口約束なんです。やはり信頼関係を大事にする人が多いんです。
この制度でかかりつけ医を持つことを希望する患者、「書類を書いてください」と言う患者がぐーんと増えて、先生方がてんてこ舞いになるということはまずないと思います。情報公開して、患者が自由に選べるようにすることがこの制度の基本だと思うんです。
松村 ありがとうございます。書類でてんてこ舞いになるんじゃないかという不安が解消されました。
「何でも相談できる先生」はいたほうがいい
大橋 よく喫茶店で話をしているおじいちゃん、おばあちゃんは、かかりつけ医の先生の自慢話をしますよね。「あの先生はここがいい」「あそこがいい」とか。みんなで評価しながら口コミで選んだりするのが日本の文化ならば、それは大事にすべきだと思います。
ただ、「心臓なら○○先生、糖尿病なら△△先生」というとマルチプロブレム、多疾患併存の患者が多い中では大変なことになるので、やはり「何でも相談できる先生」は持っているといいということはあると思います。制度で縛るのではなく、情報を集めながら自分に合ったかかりつけの先生を選んでいくようになるのが一番日本らしいやり方なのではないかと思います。
【関連動画:「クリニックの地域医療戦略シリーズ」シリーズ】
第1弾「地域フォーミュラリ・リフィル処方箋をどう活用するか」(草場鉄周×近藤太郎×小見川香代子)
第2弾「診療報酬改定2024最速解説」〈第1部〉クリニックが知っておくべき 診療報酬改定2024のポイント((小松大介)/ 〈第2部〉クリニックが押さえておくべき2024在宅報酬改定のポイント~重要ランキング10~(永井康徳)
第3弾「プライマリ・ケア薬物治療の新戦略」(今井博久×北 和也×佐々江龍一郎)