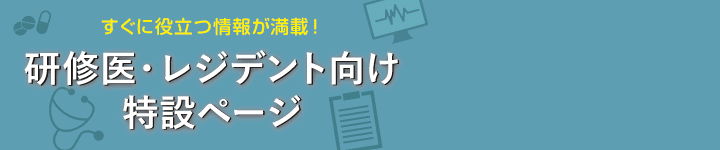お知らせ
「終末期鎮静は緩和ケアの一環」と確認─日本リビングウイル研究会
日本リビングウイル研究会は23日、終末期鎮静をテーマにシンポジウムを開催した。シンポでは、鎮静が緩和ケアに含まれることが確認された。
終末期鎮静は、がん患者の死亡直前の苦痛に対応する緩和ケアと位置付けられている一方で、患者との意思疎通ができなくなることから、その実施は患者、家族、医療チームにとって難しい選択となっている。また、鎮静を「安楽死の代替物」視する声があり、「終末期鎮静は緩和医療」というコンセンサスは社会で十分に得られていないという。同研究会はこうした現状に危機感を示し、終末期鎮静に関するシンポを企画した。

講演した聖隷三方原病院(静岡県)の森田達也副院長は、鎮静の定義について「他に緩和する方法がないときに、鎮静薬で意識を低下させて苦痛を緩和させること」と説明。「鎮静薬を使用するのは最終手段」と強調した。その上で鎮静は、治療中止とは別の判断であり、緩和ケアに含まれることを明言。原則的には苦痛緩和を目的として少量から調節して投与する調節型鎮静を行い、それでも苦痛緩和が困難なときに、深く眠ることを目的とした持続的鎮静を選択することを求めた。持続的鎮静の実施の際には、相応性、家族の意思、医療者の意図、チームによる判断を考慮すべきとした。
■療養場所による鎮静率の違いを巡り議論
長尾クリニック(兵庫県)の長尾和宏院長は、末期がんの鎮静率が、ある在宅クリニックでは1%であるのに対し、ある病院では70%にまで上ることを問題視し、「最後まで延命治療を続けた結果、苦痛が増し、鎮静するケースが多いのではないか」と指摘した。長尾氏はこうしたケースについて、「過剰医療に起因した有害事象に対して新たな過剰医療を加えていることに気付かない現代医療の落とし穴」と強調。延命治療を控えれば、持続的鎮静が必要な事例は多くないとした。
療養場所で鎮静率が違う理由については、ケアタウン小平クリニック(東京都)の山崎章郎院長が「病院では、患者の安全管理や他の患者への配慮といった観点から、鎮静の検討に入りやすいのではないか」と述べた。これに対し、森田氏は「鎮静率が高いことが必ずしも悪いのかというとそうではない」と指摘。療養場所によって患者の平均年齢や重症度が違う場合もあることから、鎮静率の比較は適切ではないとして、「個々の患者さんが何を望み、満足が得られたかという議論が大切だ」と話した。
■持続的鎮静の必要性を共有し、家族の罪悪感を軽減
シンポではまた、患者の意思を尊重して持続的鎮静を行っても、家族が罪悪感に苛まれるケースがあることを問題視。これについて山崎氏は、鎮静薬を中止・減量し、意識が低下しない時間を確保する間欠的鎮静のプロセスを踏み、目覚めた瞬間に苦しそうにするなど、患者が直面している現実を家族と共有すべきと指摘。「持続的鎮静の必要性を共有すれば、家族の後悔はなくなるのではないか」と述べた。