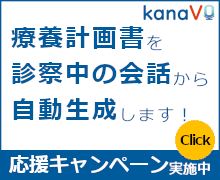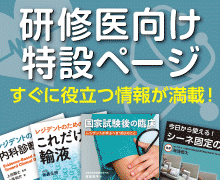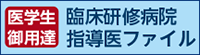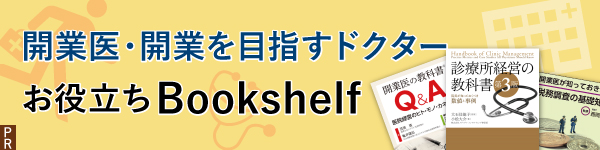お知らせ
岩田健太郎
- 登録日:
- 2020-01-17
- 最終更新日:
- 2024-05-29
「メタ認知の重要性」
こんなことを書くと、読者諸兄に怒られそうだが、最近流行りの「炎上覚悟」という言い方をするならば、医者は案外、メタ認知が苦手だと思っている。あと、霞が関の官僚諸氏も同じ病理を抱えている。
メタ認知とは、認知の認知である。自分がなぜ、そのような認識を持っているかということを外から了解する認知の方法だ。虫の目に対する、鳥の目(bird’s eye)、と換言してもよいのかもしれない。
たとえば、法制度だ。これこれこういう法律があり、通知がある。「こういう場合は、ああしなければならない」というノウハウ的な知識を、多くの医者はたくさん持っている。
しかし、そのような法律はどのような根拠でできているのか。それは施行当時から数えて、現在でもホールドできる根拠なのか、問題点はないのか。改善点はないのか。それは最良解なのか。このように吟味、検討、代案を創出する能力については、医者は案外、高くないと思っている。どちらかというと現実説明に汲々として、現実打破にはおよび腰なことも多い。
このことは、日本におけるEBMの浸透度の低さと関係しているように思う。
たとえば、肺外結核や潜在性結核(LTBI)の治療である。治療後に、保健所から「胸の画像を撮ってくれ」と要請してくることが多い。肺外結核の治療後に肺結核を発症するリスクは非常に小さい。潜在性結核の治療後に……以下同文だ(もちろん、治療前に、ならわかる)。国際的にはこのようなプラクティスは推奨されていない。しかし、厚生労働省は依然として理路もエビデンスも乏しいこうしたプラクティスを全国の保健所に要請し、保健所の保健師はこれを批判的に吟味することなく臨床現場に要請し、多くの医療者はこれを批判的に吟味することなく、漫然と患者に放射線を当て続けている。患者に害をなすなかれ(do not harm)の原則から外れる行為であり、とうてい許されることではない。ぼくはいつも「医学的に根拠が乏しい放射線を患者に照射することはいたしません」と保健所に断りを入れている。もちろん、臨床症状がこの判断を変えさせる場合はこの限りではない。
ことほど作用に、日本では「そうすることになっている」で思考が止まってしまい、なぜそうなのか、そうすることで何がもたらされるのか、というところまで思考が至らないことが多い。メタ認知の欠如であり、大いに不満とするところである。
岩田健太郎(神戸大学医学研究科感染治療学分野教授)[批判的吟味][代案創出力]
過去記事の閲覧には有料会員登録(定期購読申し込み)が必要です。
Webコンテンツサービスについて
過去記事はログインした状態でないとご利用いただけません ➡ ログイン画面へ
有料会員として定期購読したい➡ 定期購読申し込み画面へ
本コンテンツ以外のWebコンテンツや電子書籍を知りたい ➡ コンテンツ一覧へ