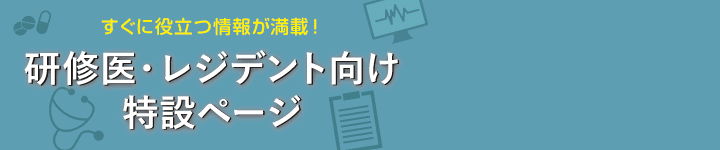お知らせ
(6)論説 高額薬剤問題への処方箋─どう使われる?費用対効果評価 [特集:「高額薬剤」問題を考える]

増分費用効果比(ICER) 費用対効果評価 追加的有用性 質調整生存年(QALY) Cancer Drugs Fund
はじめに
「とてもよく効くが、とても高い」医薬品を公的医療保険制度の中でどのように扱うか?薬の費用対効果評価、そして費用対効果評価の政策応用に関する議論は、この1、2年間で大きな転換期を迎えつつある。
半世紀以上の長きにわたって、日本では「国民皆保険制度」という言葉が「すべての国民に公的医療保険が提供される制度」という本来の定義を超えて、「その公的医療保険でほぼすべての医薬品が賄われる」状態として理解されてきた。医療費の増大に対しては、これまでは老人医療費の定額負担→定率負担→現役並み所得の高齢者の負担率引き上げや、保険料率自体の改定、健保の本人負担の自己負担率引き上げなど、「広く薄く」負担を上乗せする形で対応を試みてきた。
急速な高齢化と医療技術の発展にともない、医療費はさらなる膨張が見込まれる。限りある医療資源の適正配分を目指して、諸外国では安全性や有効性に加えて、効率性・費用対効果のデータが求められるようになってきた。
日本でも、2012年に中医協(中央社会保険医療協議会)に費用対効果評価専門部会が設置され、どのような形で費用対効果のデータを医療保険制度に組み込みうるかの議論がなされてきた。
そして、2016年4月から「試行的導入」として、上市済みの医薬品・医療機器のうち予測売上高・加算率など一定の条件を満たした品目を指定し、企業に費用対効果のデータ提出を求めている。企業から提出されたデータと外部専門家などが再分析したデータの双方を吟味した上で、費用対効果以外の倫理的な要素なども考慮し、最終的な評価結果を次回(2018年4月)の診療報酬改定の際に反映させる予定である。
費用対効果評価の試行的導入では、結果の活用は「既存品目」の「価格調整」に限定されている。しかし、諸外国では新薬をターゲットとし、給付の可否や価格調整に使われることがむしろ主流である。日本でも2016年10月から、一定の基準を満たす新薬についても費用対効果のデータが求められる。
これまで日本では、「医療にオカネの話を持ち込むべきでない」「海外と違って費用対効果の考え方はなじまない」のような、ある意味情動的な意見も少なくなかった。しかしこの1、2年間に「とてもよく効き、なおかつとても高額」な薬の上市が相次いだことで議論の風潮は大きく変わった。議論の風向きを変えるのに大きく“貢献“した3剤が、C型肝炎治療薬のソバルディ(ソホスブビル)、がん免疫療法薬のオプジーボ(ニボルマブ)、高コレステロール血症治療薬のレパーサ(エボロクマブ)である。
2015年5月に上市されたソバルディは、12週間(84日)の服用期間で有効率(SVR達成率)は95%以上だが、上市時点での薬価が12週間で約500万円と高額であること、また対象患者数が多く、医療財政への影響が大きいことが議論の的となった。
続いてオプジーボである。2014年9月に、メラノーマ(悪性黒色腫)の治療薬として薬価収載された際には、適応患者数が少ないこともあり(企業提出資料ではピーク時患者数は470人)、費用の問題はそれほど論点になっていなかった。しかし、2015年12月に非小細胞肺がんに適応拡大されると、薬価の高さと医療財政への影響の双方が議論になった。
「年間3500万円で5万人が使用すると、オプジーボ単剤で1兆7500億円に達する」のような試算も広範囲に報じられた。オプジーボの肺がん患者への臨床試験結果は、全生存期間でも中央値としてオプジーボ9.2カ月、比較対照ドセタキセル6.0カ月であり、「5万人が1年間オプジーボを使い続ける」という仮定はやや過大にも見える。ただ、適応拡大によって医療財政への影響が激変したことに、現行の薬価算定システムが対応しきれないことが、議論のきっかけとなったことは間違いない。3カ月投与すれば終わりのソバルディとは異なり、投与終了のタイミングを見極めるのが難しいことも、オプジーボにとって不利な点となった。
そしてレパーサだ。2016年4月に高コレステロール血症の治療薬として薬価収載され、1年間の薬価は約50万円と、ソバルディ、オプジーボと比較すればかなり低額である。しかし、対象疾患が生活習慣病であり、想定患者数が膨大になることから、中医協の場でも適応患者を家族性高コレステロール血症に限定すべきなどの意見が出た。
注目すべきは、これら高額な薬剤のあり方を議論する際に、医療財政への影響を問題視する意見、保険適用の制限を主張する意見が、保険者のみならず医療提供者側からも出てきたことである。今までのように「すべての医薬品が保険でカバーされる」制度を聖域化する議論から、財政状況その他を考慮しつつ最適な医療システムを維持していく方法を考える方向へ世論が転換したことの意義は大きい。その意味で筆者は先の3剤を、講演等で“黒船”と表現している。
費用対効果評価=英国NICEの評価?
費用対効果評価の議論は、導入すべきか否かの段階から「医療制度の中でどこに、どのように導入すべきか?」の段階に移行しつつある。政策応用を考える際に常に話題に上るのが、英国の医療技術評価(Health Technology Assessment:HTA)機関、NICE(The National Institute of Health and Care Excellence)のシステムである。
周知のとおり英国では、公的医療制度・国民医療サービス(The National Health Service:NHS)での給付の可否の判断に経済評価を用いる。保健省が指定した薬剤に対しNICEが評価を行い、推奨・非推奨の判断を下す。
NICEが評価を下す際の薬剤の効き目のものさしとしては、生活の質(QOL)で重み付けした生存年「質調整生存年(QALY)」を用いるのが必須で、1QALY増やすのにかかる追加費用である「増分費用効果比(ICER)」を計算して評価する。ICERの値は小さければ小さいほど「費用対効果に優れる」とされるが、NICEの分析ガイドラインによれば、「1QALYあたり2万~3万ポンド」がICERの上限値、すなわち閾値とされる1)。
知名度では英国NICEのシステムが抜きん出ていることもあり、「英国は1QALYあたりのICERを計算して、閾値をあてはめて一律に給付する・しないを断ずる」、さらには、「QALYを使って費用対効果を評価するから、医薬品への給付制限が生じる」「QALYのような単位を使うのはNICEのみ」「費用対効果評価の導入はアクセス制限につながる」など、費用対効果評価導入の「悪しき例」として紹介されることも多い。
しかし、巷間言われる「悪しき例」の多くは、費用対効果評価そのものや、HTA機関の機能、QALYの利用法に関する誤解に起因するものである。以下、よくある誤解を紹介しつつ、費用対効果評価の実際の応用例を議論していきたい。
残り6,257文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する