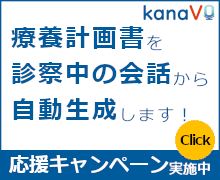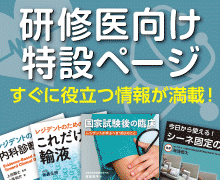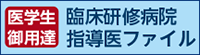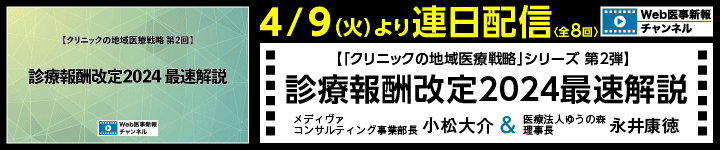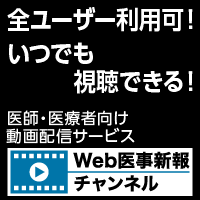お知らせ
【識者の眼】「誰もが希望を持てる社会とする最善策」小倉和也
No.5140 (2022年10月29日発行) P.58
小倉和也 (NPO地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク共同代表、医療法人はちのへファミリークリニック理事長)
登録日: 2022-10-06
最終更新日: 2022-10-06
- コーナー: OPINION
- 医療界を読み解く[識者の眼]
経済発展と女性の就業率の上昇は少子化につながるという“常識”はもはや“古い常識”でしかないとの指摘が注目されている1)。この常識が先進国の状況を反映していたのは80年代までであり、その後は女性が働いた場合でも、子育てがしやすい環境を整えることができた国では、むしろ就業率とともに出生率は高くなっているという。
整えるべき環境とは、①公的保育と家族支援策、②男性の育児参画の増加、③女性の就労を肯定する社会規範、④流動的雇用市場、の4つとされている。子育て世代の女性を雇用する立場としてもまさにその通りであると感じる。
女性職員が産休・育休を取得し復職するにあたっては、まず保育園が見つかることが前提となる。運よく見つかった場合でも、子どもが発熱した場合に妻をサポートできる環境が夫側にも整っているかなども重要だ。さらに家庭内はもちろん、あらゆるところで女性が就労することを肯定する、少なくとも否定しない社会であることが求められる。子どもが発熱して受診した小児科で、「普通こんな小さな子を預けて仕事しないでしょ」と言われた職員もいた。
上記の条件がクリアでき、無事復職できた場合も、非常勤となる場合がほとんどで、その際には税制などの問題から就業時間を増やすことがむしろ制限される。経験を積みキャリアアップを図ろうとしても、その間継続して働く職員や男性と差が付きやすく、日本社会全体の雇用のあり方自体が能力の発揮を阻んでいると感じる。
少子高齢化で労働力も不足し、社会全体が閉塞感に苛まれる現在の日本は、また世界で最も有能な人材、特に女性の能力を活かしきれていない国でもあるのではなかろうか。その能力を活かせる環境をつくることが、女性だけでなく男性、子ども、高齢者も含め希望が持てる社会とするための最善かつ唯一の方法と考える。
【文献】
1)https://www.nber.org/papers/w29948
小倉和也(NPO地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク共同代表、医療法人はちのへファミリークリニック理事長)[女性の就業]