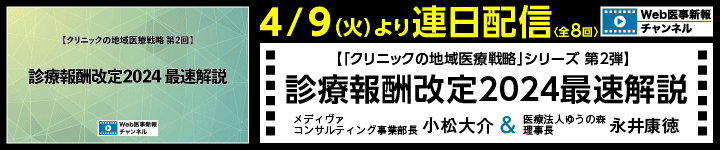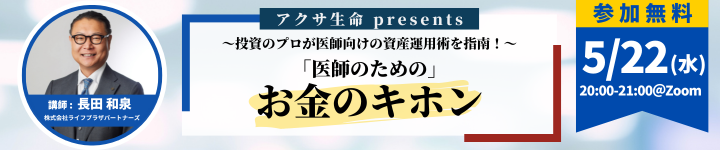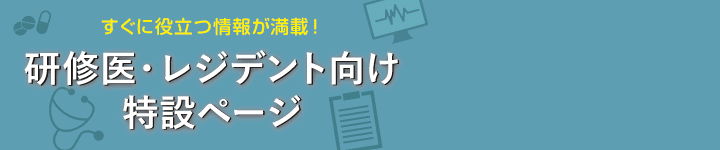お知らせ
高木兼寛(5)[連載小説「群星光芒」307]
「英国で本格的な医療を研鑽したい」
そう望んでいた高木兼寛に海軍病院学舎のアンダーソン医師から願ってもない話がもたらされた。
「Youはイギリスに留学してはどうか?」
と勧められたのだ。
「いまや海軍病院の患者の3/4はBeri- beriである。この難症の原因と治療法を見つけるためにイギリスへいって研鑽をつむのもよかろう」
そしてアンダーソンはつけくわえた。
「既に海軍省の幹部にカネヒロが留学できるよう話をつけてある」
英国留学が実現するとはなんという僥倖だろう。これまで医師の留学先といえばほとんどがドイツであり、イギリス留学を果たした医師は誰もいなかった。
実は鹿児島藩では安政4(1857)年頃、進取の気性に富む藩主の島津斉彬侯がイギリスに留学生を派遣する構想を抱いた。だが、外国留学は国禁を犯すことであり、しかも斉彬侯が急逝したことから計画は頓挫した。
しかし藩の首脳たちはあきらめなかった。斉彬侯の遺志を継ごうと元治2(1865)年3月に15人の留学生をロンドンに送り込んだ。
その中に鹿児島藩医の田中静洲(23歳)と中村宗見(22歳)がいた。ところがロンドンにしばらく滞在した2人はまもなく居場所をパリに移し、フランス留学に替えてしまった。帰国した田中と中村はフランス語の達人として新政府の通訳や外交の場で活躍したが、医療に関わることはなかった。
兼寛が海軍省より正式に英国留学を命ぜられたのは明治8(1875)年6月だった。
留学先はアンダーソンの母校であるロンドンのセント・ト-マス病院医学校に決まった。
同校はロンドン市庁舎の近くのテムズ河畔にあり、対岸には国会議事堂がそびえる市の中心部に位置していた。
医学校の寄宿舎に居住した兼寛は、「最初の日本人医学生として名を辱めてはなるまい」と講義や実習に励んだ。
とりわけ病室や外来に脚気病を思わせる患者がいるか注意を払ったが、それらしい患者に出会ったことはなかった。
学生指導のドクターに質問しても、「英国ではそのような病気を診たことがない。BeriberiはJapan特有の風土病ではないか」と片づけられた。
栄養学の授業には特に耳をかたむけた。教師は英国衛生学界の権威E・A・パークス教授の弟子だった。講義の中で教師は言った。
「人の健康を維持するために理想的な食事とは窒素と炭素の割合、すなわち、蛋白質と炭水化物を1:15とすることである」
これをきいて兼寛は、「日本人の食事もこの割合を参考にすれば英国人同様、脚気病を防げるのではないか」と思い、「帰国したら、ぜひ試みてみよう」と考えた。
セント・トーマス病院にはクリミア戦争で傷病兵の看護に尽くしたフローレンス・ナイチンゲールが働いていた。
ミス・フローレンスは1854年のクリミア戦争で多くの傷病兵の看護に尽くしたことから、ヨーロッパ中でその名が知られていた。野戦病院では夜間も患者の容子を見て回ったことから、「ランプを持ったレディ」、「クリミアの天使」と讃えられた。
「ミス・フローレンスは、1856年にイギリスのヴィクトリア女王に拝謁して、各地の病院の環境整備や患者の食事改善を献策しています」
「フローレンス女史は女王様の賛同を得てこのセント・ト-マス病院に世界最初の看護婦養成所Nightingale Homeを創立したのです」と、ナースたちは誇らしげに兼寛に話した。
病院の事務員たちもこんな話を伝えた。
「ミス・フローレンスは勝気な方で少しくらいではへこたれません。1日20時間も働きづめだったので、41歳のとき過労と心労で歩行困難になりました。それでも車椅子に乗ってナースの指導に当たっているのは頭がさがります」。そう言ってから少し小声で、「ただし理想が高いせいか手法に強引なところがあり、我々事務員とはしばしば衝突します」と苦言をもらした。
兼寛が初めてナイチンゲールに会ったのは病院の中庭だった。50代半ばを過ぎた彼女は思ったより小柄で、車椅子に乗りながら小児病棟の子どもたちの日光浴を見守っていた。兼寛は「ミス・フローレンス」と呼びかけて会話を交わした。
「この病院ではNurseが患者のためにてきぱきと働き、Doctorをよくsupportする姿に感心しました」
そういって感想を述べると、それがうれしいときの癖なのか、彼女は皺の寄った口唇をすぼめてうなずいた。
「日本には患者を看護する職種がないので、帰国したあかつきにはぜひともNurseを養成する学校を設けたいと思います」
すると、彼女は車椅子から立ち上がらんばかりに相好を崩し、「わたしは貴方を心から支援します」と、張りのある声で兼寛を励ました。
セント・ト-マス病院医学校では、高学年の生徒に英国紳士としての洗練されたマナーや社交ダンスを教えた。兼寛もワルツのステップが踏めるようになった。
教師の案内で英国海軍医学校を見学する機会もあり、海軍軍医の粋でスマートな勤務ぶりを垣間見ることができた。
5年間の在学中、兼寛の学業成績は抜群だった。卒業の際は同校の校長から最優秀医学生の表彰を受け、また、各種の賞金と賞状を授与された。ロンドン内科医師会からもDiploma(免許状)を、英国外科医師会からはFellowship(特別研究員)を与えられた。そして、英国産科医の資格と英国医学校の外科学教授の資格をも取得した。
兼寛がイギリスから帰朝したのは明治13(1880)年11月5日だった。
5年ぶりに夫の顔をみた富子は、ふっくらとした頰に安堵の色をうかべて泪を流した。数え9歳の長男喜寛も背が伸びて、「父上、お帰りなさい」と礼儀正しく挨拶する姿が頼もしかった。